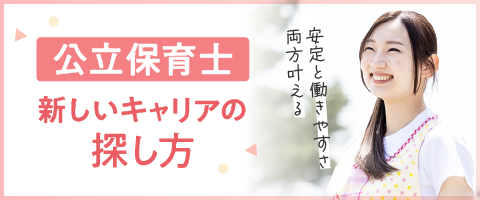保育園を新たに運営したいと考える事業者や経営者の間で、既存の園を買収(M&A)する方法が注目されています。少子化や保育制度の変化の中で、保育園の経営は新規開設よりもM&Aによる参入が現実的という考え方もあるでしょう。本記事では、保育園を買収・承継する際の基本的な流れや基礎知識、知っておきたい制度や注意点、保育園買収・承継のメリット、実際のM&Aスキームまでを幅広く解説します。
 buritora / stock.adobe.com
buritora / stock.adobe.com
保育園の買収が注目される背景
子育て支援のニーズが高まり続ける中、保育業界は今なお社会的意義と安定した需要を兼ね備えた分野として注目されています。
特に、共働き世帯の増加や企業の福利厚生強化の流れを受けて、異業種からの参入も増えています。
こうした背景のもと、「新規開設」ではなく「既存園の買収(M&A)」という形で保育園運営を始める動きが広がりつつあります。
実績ある施設を引き継ぐことで、参入のリスクを抑えながらスピード感ある展開が可能になっているといえるでしょう。
ここでは、保育園の運営において「買収・承継」が注目されている理由と、その背景についてみていきましょう。
保育園新設の難易度上昇
保育事業は社会的ニーズが高い一方、認可取得のための行政調整や国家資格保有者である保育士の確保が難しく、新規参入には多くの壁があります。
特に認可保育園の設立には、国が定めた施設・設備基準の遵守、自治体との調整、各都道府県知事の認可を得るための申請スケジュールへの長期的な対応が不可欠で、2~3年単位の準備期間が必要です。
そのため、既存の保育園を買収し、すでに整った運営体制・許認可・人材・保護者との関係をそのまま引き継げるM&Aは、現実的かつ効率的な参入手段として注目されているのです。
少子化による需要減と施設過多
厚生労働省の統計によると、2024年の出生数は68万6,061人と9年連続で過去最少を記録し、今後も減少傾向が続くと見られています。
一方、待機児童対策として保育施設数はこの10年で約1.4倍に増加していることから、地域によってはすでに定員割れも発生し、運営継続が難しい園の売却ニーズが高まっています。
また、都市部では一部の人気保育園に入園希望が集中し、希望する園に入れない「隠れ待機児童」が増加しているという問題も浮上しています。
入園希望者や地域のニーズをくみ取った保育園運営を行うことで、この問題解決にも貢献できる可能性が高いでしょう。
後継者不在や経営者高齢化による売却案件の増加
保育園を運営している法人や個人経営者の多くが高齢化を迎えており、後継者が見つからずに事業承継を検討する動きが活発化しています。
中小企業庁の調査では、60代以上の経営者の約4割が「後継者未定」と回答しており、保育園業界でもこの流れは顕著といえるでしょう。保育園のM&Aについて問い合わせる
お問合せ&資料ダウンロード
採用課題・経営課題に関する個別ご相談受付やサービスガイドなどの資料DLはこちらからどうぞ。
まずはお気軽にお問合せください!
保育園業界の市場規模と動向
 Paylessimages / stock.adobe.com
Paylessimages / stock.adobe.com
保育業界はここ数年で構造的な転換期を迎えています。これまで国の支援を受けて施設数を拡大してきましたが、出生数の減少が加速しており、今後は淘汰と再編の時代に入ると見られています。
厚生労働省によると、2022年4月時点で保育園等の数は全国に39,244カ所となり、前年から578カ所の増加が確認されています。
一方で、2024年の出生数は68万6,061人と過去最少を記録しており、人口動態の観点からは将来的な園児数の減少が予測されています。
こうした状況から、今後は保育園を新設するのではなく、既存施設の買収・承継による再活用の重要性が高まることが考えられるでしょう。
保育園の種類と各施設の特徴
保育園と一口にいっても、運営主体や制度の違いにより、買収・承継プロセスに大きな差があります。
買収・承継を検討する際には、対象となる施設の種別と、法的および行政の制約を正しく理解しておくことが不可欠です。
主な保育施設の分類
施設の「認可の有無」「法人形態」「行政との関係性」が、スムーズな買収・承継に直結するポイントです。
|
種類 |
認可の有無 |
主な運営主体 |
買収対象として |
|
認可保育園 |
あり |
社会福祉法人/株式会社など |
行政手続きが多くやや難しい |
|
認可外保育園 |
なし |
株式会社/NPO法人/個人 |
比較的容易 |
|
企業主導型保育園 |
あり |
法人・企業 |
中程度の難易度 |
|
小規模保育事業(A型等) |
あり |
社会福祉法人/NPO法人など |
自治体の支援制度に依存するためやや難しい |
認可保育園
児童福祉法に基づき、国が定めた設置基準・職員配置・保育内容を満たしたうえで、各都道府県の認可を取得する必要があります。
対象児童は主に0歳児~5歳児で、自治体の主導のもと共働き家庭やひとり親など、保育の必要性が認められる家庭が優先して入園します。
入園には保育認定と自治体ごとに定める点数制での選定があるため、利用希望者が多い都市部では入園競争が激しい傾向があります。
認可外保育園(企業主導型・認証保育園など含む)
認可外保育園は自治体の認可を受けず、比較的自由な運営が可能です。
企業主導型は国の助成を受けつつ、従業員と地域住民の子どもを受け入れ、柔軟な保育体制を特徴としています。
また、東京都などで展開する「認証保育園」もこれに該当し、各自治体独自の基準に基づいて都市部の保育需要を補完しています。
小規模保育事業(A型・B型・C型)
子ども・子育て支援法に基づく地域型保育事業で、原則として19人以下の0~2歳児を対象とした少人数で保育を行う施設です。
A型は保育士配置義務があり、B・C型は柔軟な人材配置が可能です。家庭的な雰囲気が強く、自治体によっては待機児童対策として誘致・支援が進んでいるケースもみられます。
認定こども園
幼稚園と保育園を一体化した制度で、学校教育法・児童福祉法の双方に準拠する施設です。自治体の認定や教育課程の設定など、設立・運営に専門性が求められます。
施設形態によっては保育の必要性の認定に関わらず利用でき、保育ニーズの多様化に対応しているのが特徴です。
保育士バンク!の新着求人
お住まいの地域を選択して、最新の求人情報をチェック!
選択済みの市区町村
保育事業へ参入するメリット
保育園運営について検討する際、近年の出生数の減少だけを見て「今後は保育ニーズが縮小傾向=事業価値が低い」と判断するのは早計といえます。
むしろ共働き世帯の増加や、保育の多様化を支援する新制度により、利用者数の底上げが期待される状況に注目している経営者は多いようです。
次からは、保育業界に参入するメリットを見ていきましょう。
高水準の保育園等利用率と定員充足率
保育サービスの市場環境を見るうえで、保育園等の利用率と定員充足率の高さは注目すべきポイントです。
厚生労働省の資料によると、2024年4月時点で、就学前児童に対する保育園等の利用率は54.1%と過半数を超え、特に1・2歳児では59.3%と高い水準を記録しています。
保育の必要性が高まるなか、共働き世帯だけでなく、短時間勤務や在宅就労の家庭など、多様な層からのニーズが広がっていることがうかがえます。
また、前章でも示したとおり、施設の定員充足率は88.8%と、全国的に安定した稼働率を維持しており、施設運営の視点でも高い効率性が保たれています。
これは、買収・承継や事業参入後においても、一定の需要が見込める基盤が整っていることを示しており、参入戦略における安心材料となり得るでしょう。
統計に現れない「隠れ待機児童」ニーズ
2024年4月時点の全国の待機児童数は2,567人と減少傾向にありますが、都市部や人気エリアでは依然として保育ニーズに供給が追いついていない状況です。
特に問題なのが、統計に現れない「隠れ待機児童」の存在です。
これは、希望する園に入れなかったことで、ほかの園への入園内定を辞退するケースなどが該当します。
このようなケースは国や自治体がカウントする待機児童数には含まれないため、具体的な数は公表されておらず、表面上の待機児童数以上に潜在化している実態があるようです。
背景には、「兄弟で同じ園に通わせたい」「自宅や職場の近くで延長保育付き」「小規模で幼児教育が充実している園を希望」など、保護者ニーズの多様化があります。
このようなケースからは、待機児童問題が解消され、単に預けられればよいというニーズが満たされたことから、さらに具体的な要望をかなえられる保育を求める声が増えている現状が読み取れるでしょう。
地域特性や時流にあわせた展開を踏まえたフレキシブルな運営が、今後の保育事業成功の鍵となりそうです。
2026年度から「こども誰でも通園制度」開始
保育業界参入のメリットとして挙げられるさらなる一例が、2026年度から全国展開される「こども誰でも通園制度」です。
この制度は、こども家庭庁が進める施策で、認可保育園等を利用していない家庭の子どもも、一時的に保育サービスを利用できる仕組みで、2023年度から一部自治体で先行実施、2026年度から全国で本格実施されます。
この制度により、専業主婦世帯や短時間勤務の家庭などの利用ニーズが顕在化し、今後も保育サービスの裾野拡大が進むことが見込まれています。
したがって、たとえ出生数が減少傾向にあっても、保育の利用機会が拡大する可能性は高く、買収・承継によって既存資産を活用しながら事業に参入することは、依然として有効な戦略と言えるでしょう。
読んでおきたいおすすめ記事

【採用担当者向けコラム】保育学生はここを見る!新卒採用につながるSNS活用術と「選ばれる園」になる3つの条件
この時期でも、保育士の新卒採用に悩んでいる保育園経営者の方も多いのではないでしょうか。2026卒採用を叶える成功のカギは、SNSを活用しつつ「園見学・先輩の声」で園の魅力を伝えながら、学生が求める「安...

【採用担当必見】保育施設のお悩み対策診断。今、あなたの園に必要な対策は?
保育施設の運営にまつわる課題は、採用・定着・園児集客など、園によって本当にさまざまです。一体、自園にとって必要な対策は何なのか?「保育施設のお悩み対策診断」を使って調べてみましょう。 &n...

【採用担当者向けコラム】保育士の意向調査実施マニュアル。来年度に向けた準備のポイント
保育士さんに向けて来年度の就業意思を確認する意向調査では、どんなことに配慮して進めるとよいでしょうか。今後の園の運営や保育士さんの育成に関わることなので、慎重に行なうことが大切です。今回は、意向調査の...

【採用担当者向けコラム】意向調査で「退職希望」を示している保育士の引き止めはできる?
意向調査で退職の希望を示している保育士さんの引き止め方を知りたいと感じる採用担当者の方もいるでしょう。保育士不足が続く中、頼りにしていた保育士さんが抜けてしまうと運営が苦しくなりますよね。今回は、意向...

【2024最新】保育士不足が続く原因は?解消に向けた国・自治体・園の対策も解説
なぜ保育士不足が続くのでしょうか。子育て支援の重要性が増す中で、資格を持ちながらも保育士として就業する人が少ない状況を受け、国や自治体ではさまざまな対策を行なっています。今回は、深刻な社会問題でありな...

【2024年最新】学童保育の補助金はいくら?開業や運営に関わる助成金について
全国的に共働き家庭が増えたことで、小学生の居場所となる学童保育の拡充が求められています。実際に学童保育の開業や運営を目指す場合、国や自治体からいくらの補助金を受け取れるのでしょうか。今回は、学童保育の...

【採用担当者向けコラム】保育士の人材紹介手数料は高い?相場や会社による違いを解説!
保育士採用でも利用される「人材紹介」。手数料が何十万にも上ったという話を聞き、利用を迷っている採用担当者の方もいるかもしれません。今回は、保育士の人材紹介について、手数料の相場と費用が高いと言われる理...

【採用担当者向けコラム】真面目な人ほど急に辞めるのはなぜ?保育士が突然退職する理由と対策
真面目な人から急に辞めると告げられて、「何がよくなかったのか…」と頭を抱える採用担当者の方もいるのではないでしょうか。おとなしい人や優秀で勤勉な保育士さんほど、職場にストレスを抱えているかもしれません...

【採用担当者向けコラム】人材紹介会社が保育士さんを紹介してくれないのはなぜ?原因と対策
人材紹介会社を利用したにもかかわらず「保育士さんを紹介してくれない」と悩みを抱える方はいませんか?採用活動がスムーズに進まないと人材不足が解消されず、運営に支障をきたすケースも。今回は人材紹介会社から...

転職フェア出展は意味がない?採用できない?保育士を集客するためのポイント
多くの保育士さんと出会い、自園の魅力を直接伝えられる「転職フェア」。人材確保のチャンスになる機会ですが、出展しても意味がないのでは、採用できないのではと不安を抱く方もいるでしょう。今回は、転職フェアで...

放課後等デイサービスの職員採用の方法は?求める人材に出会うコツ
保育・福祉業界では人材不足が深刻化しており、放課後等デイサービスについても採用に苦戦する施設があるでしょう。特に児童発達支援管理責任者(児発管)の不足は、全国的に大きな課題となっています。今回は、放課...

時短勤務とは?保育園が導入するメリット・デメリットや注意点
2009年度の育児・介護休業法によって制度化された「時短勤務」。正式には短時間勤務制度と呼ばれ、3歳に満たない子を療育する労働者を対象に多くの方が利用しています。今回は時短勤務の概要や対象者、導入状況...

学童保育の経営に必要な基礎知識!開業の流れや必要コスト、成功のポイント
学童保育の開業を考えている方は、開業の流れやランニングコストの目安を把握しておくことが大切です。学童保育を経営するうえで必要な基礎知識をチェックしていきましょう。今回は、学童保育の経営に関する内容や成...

【採用担当者向けコラム】保育士採用で合同説明会に出展するメリット。成功の秘訣
保育事業者にとって合同説明会への出展には、どのようなメリットがあるのでしょうか。採用の成功率をアップするために、出展を検討する採用担当者の方もいるかもしれません。今回は保育士さん向けの合同説明会の活用...

学童保育の採用に人材紹介サービスを利用するメリットと注意点。活用するポイント
学童保育の採用に人材紹介サービスを利用するべきかと悩む事業者の方はいませんか。「手数料が高いのでは?」「希望する人材の紹介が受けられるのか」と不安を抱くこともあるでしょう。今回は、学童保育の採用に人材...

【採用担当者向けコラム】退職代行を使われた時はどうする?保育園に連絡が来た時の対処法
職員から退職代行サービスを利用して退職の申し入れがあった場合、どのように対処すればよいのでしょうか。連絡が来た時点で直接該当の職員とやり取りすることが難しいため、戸惑ってしまいますよね。今回は退職代行...

ジョハリの窓とは?4つの窓の内容や注意点、具体例をわかりやすく解説
「ジョハリの窓」という自己分析ツールはご存じですか。「開放」「秘密」「盲点」「未知」の4つの窓を用いて、自分や他者からの印象を認識していく手法です。今回は、ジョハリの窓の概要や企業内での導入時の注意点...

今、重要視される「学び直し」は保育士に必要?園側が取り組む具体例
社会人の学び直しが注目されている昨今、雇用側の環境整備が求められます。今回は、保育士の学び直しが必要なのか、園側の取り組みや具体例についてわかりやすく解説します。保育士がやりがいをもって働ける職場を作...

人的資本経営とは?保育園経営に活用するメリットや保育士育成のポイント
人的資本経営とは、企業の人材を「資本」と捉え、人材の価値を高めることで企業価値の向上を目指す経営手法です。近年注目されている経営手法のひとつで、さまざまな企業で導入されています。今回は、人的資本経営の...

学童保育を開業するために必要な資格・条件・補助金制度について徹底解説!
全国的に学童保育の拡充が求められている今、学童保育施設を開業するためには何が必要なのでしょうか。今回は学童保育の開業に必要な条件や手続き、補助金制度などを紹介します。学童保育の開業は主に自治体から業務...
- 同じカテゴリの記事一覧へ
保育園経営をするなら買収・承継が最適な理由
 yukinoshirokuma / stock.adobe.com
yukinoshirokuma / stock.adobe.com
保育園の買収・承継は、新規開設に比べて物理・人的資源をそのまま活用できる点がポイントです。
行政対応や利用者対応を含めた運営ノウハウも引き継ぐことができるため、事業の立ち上がりもスムーズでしょう。
施設・保護者・職員ごと引き継げる
「株式譲渡」方式を採用する場合、買収・承継では運営法人そのものを引き継ぐかたちになります。この場合は、設備や運営ノウハウ、職員雇用契約などを承継することも可能です。
これにより、開園準備にかかる時間や手間を大幅に削減できます。
また、認可保育園であれば、許認可がすでにおりている施設・設備や職員数をそのまま引き継ぐことで、承継後の国への認可申請が通りやすくなるというメリットもありそうです。
また、保育士や栄養士、事務員など既存職員が継続勤務することで、園児や保護者にとっても安心感が生まれ、利用継続率の低下を防ぐことにもつながります。
現場のノウハウ・運営実績の継承によるリスク回避
保育園経営は、単純に「施設を用意して人を雇えばよい」というものではなく、保育計画の立案や日々の事故防止対応、職員間の連携、保護者対応など、現場で培われた知見の積み重ねが非常に重要です。
買収・承継によって、これらの「見えない資産」をそのまま引き継ぐことで、ノウハウ不足による初期トラブルや職員の離職リスクを最小限に抑えることができます。
資産や設備を活かしたスピーディーな事業展開が可能
保育園を一から開設するには、土地取得・建設・人材採用・認可取得など、準備期間を要します。
一方で、M&Aによる買収・承継であれば、すでに稼働している施設・体制・顧客基盤を活かすことで、事業展開を開始できる場合もあります。
特に複数園の展開を目指す事業者にとっては、拠点数を加速度的に増やす手段となります。
スピード感をもって地域展開やブランド浸透を図りたい企業にとって、大きなアドバンテージとなるでしょう。
当社ネクストビートでは、長年にわたって保育現場と向き合ってきた経験を活かし、事業者の思いや保育士の声、行政対応までを含めたていねいな引き継ぎ支援を行っています。保育園の事業承継について相談する
【M&Aの流れと手法】保育園買収・承継の基本ステップ
保育園の買収・承継は、一般的な企業M&Aと同様に、複数のステップと専門的な手続きが必要です。
とくに保育事業は、法制度や自治体との関係性が深いため、慎重な事前準備とスキームの選定が求められる点が特徴的です。
ここでは、保育園・承継の一般的な進行フローと主なM&A手法について整理します。
基本的なM&Aのプロセス
以下のフローチャートにしたがって、M&A完了までのプロセスの一例をみていきましょう。
仲介会社・専門家への相談
保育園M&Aに精通した仲介会社や弁護士・税理士などの専門家に相談し、現実的な目標設定と市場調査を行います。
承継する企業・法人の選定と交渉
希望条件に合う譲受先を仲介会社等とともに選定し、初期交渉を通じて双方の条件や意向を確認します。
秘密保持契約と基本合意書の締結
情報開示に先立ち秘密保持契約を締結し、譲渡条件の調整を行った上で、価格や時期をまとめた基本合意書を交わします。
デューデリジェンス(法務・財務調査)
財務状況・契約関係・雇用・許認可などを詳細に精査し、買収の妥当性を判断します。
最終的な契約締結
デューデリジェンス後に条件を確定し、譲渡金額や引継内容などを明記した最終契約書を締結します。
最終契約・クロージング
最終契約を結び、資産・契約・運営権などの引き渡しと対価の支払いをもって、買収・承継が完了します。
M&A手法の種類と各プロセス
保育園の買収・承継では、対象法人の種類や事業スコープに応じて、以下のような手法が用いられます。
株式譲渡
法人本体ごと買収し、園の認可・契約・資産・職員をすべて承継する方法です。
株式譲渡の基本プロセス
- 売主と株式譲渡契約を締結
- 法人の全株式を取得
- 法人ごと承継(認可・施設・人材・契約を含む)
- クロージング
この方法は、契約や行政手続きの変更が少なく、もっともスムーズかつ実務的とされます。特に認可保育園においては、法人が変わらないため認可も継続されやすいのが利点です。
事業譲渡
法人のなかから保育事業のみを切り出して承継する手法です。
事業譲渡の基本プロセス
- 売主と事業譲渡契約を締結
- 保育事業の資産・業務・職員等を個別に引き継ぐ
- 必要な許認可の再取得・契約の再締結
- クロージング
部分的な引き継ぎが可能である反面、保育士雇用契約の再締結や施設賃貸契約の巻き直しなどが発生しやすく、実務負荷が高くなることもあります。
理事交代(社会福祉法人)
社会福祉法人は非営利運営のため、買収ではなく経営の「譲渡」や「合併」になります。このため、経営権を取得する場合は「理事会の構成を変更する」という手段を用います。
理事交代の基本プロセス
- 現理事と調整し、理事交代を提案
- 新理事の選任(理事会で承認)
- 理事会構成を変更して実質的な経営権を取得
- 体制変更の届出・運営開始
この手法は、社会福祉法人の制限下で経営権を取得できる手段ですが、理事会内部での合意形成や関係者との調整が重要となってくるでしょう。
【株式会社・各種法人の違い】運営形態別の注意点
保育園の買収・承継を行う際には、運営母体である法人の種類によって、承継の可能性や手続き、譲渡価格についての考え方が大きく異なります。
ここでは、主な法人形態である株式会社・社会福祉法人・NPO法人、それぞれの違いと注意点を整理します。
【M&Aの特徴と注意点】株式会社による保育園
株式会社が運営する保育園は、もっともM&Aが実行しやすい法人形態です。
買収側が株式を取得する「株式譲渡」は、法人の経営権をそのまま引き継ぐことで補助金・従業員・契約が包括的に承継されます。特定の事業や資産を切り分けて引き継ぐ「事業譲渡」も選択可能です。
- 株式譲渡・事業譲渡のいずれかを選択
- 営利事業としての保育園運営が可能
- 売却価格の算定にあたっては、営業利益や永続的なキャッシュフローを基に企業価値を評価
また、買収・承継後に経営戦略を柔軟に変更しやすく、事業拡大やブランディングの観点からも自由度が高いのが特徴です。
一方で注意が必要なのは、M&Aによる経営母体の変更が、保護者や自治体からの信頼に影響を及ぼす可能性がある点です。
特に保育業界は高い公共性が求められることから、営利企業への不安や反発が起こるケースもあります。
また、株式譲渡では簿外債務(帳簿に記載されていない借入や未払費用)や訴訟リスクなど、引き継がれるリスクの洗い出しが不十分な場合、買収後に想定外のトラブルに発展することもあります。
M&Aを進める際には、財務・法務・人事面のデューデリジェンスを丁寧に行い、関係者とのコミュニケーションを慎重に重ねることが大切です。
【M&Aの注意点】社会福祉法人による保育園
社会福祉法人は「社会福祉法」に基づく非営利法人であり、営利目的の売却は法律上制限されています。
そのため、M&Aにおいては一般的な株式譲渡は不可能で、以下のような手法を取ることになります。
- 合併:法人の統合。認可権限を持つ所轄庁のうち、通常は都道府県知事の認可が必要
- 事業譲渡:施設単位の譲渡。行政の許可と財産評価が必須
- 理事交代:理事構成を変更し、実質的な経営権を取得する手法
社会福祉法人の基本財産(建物・土地など)の多くは、国や自治体の補助金で整備されており、自由な譲渡や売却はできません。
また、解散時には「残余財産を国または他の社会福祉法人へ帰属させなければならない」旨が、社会福祉法で明記されています。
さらに注意点として付け加えたいのが「特別の利益供与の禁止」です。
これは、社会福祉法第27条に基づき、法人の理事・監事・職員またはその親族などに対して、法人の資産や利益を不当に提供してはならないという規定です。
このような制約があるため、社会福祉法人のM&Aは、単に価格を交渉するだけでなく、公益性と適法性を維持した運営体制の構築が必須となります。
【M&Aの注意点】NPO法人による保育園
NPO法人(特定非営利活動法人)は、特定非営利活動促進法に基づく法人であり、一定の公益性を有した事業を行うものです。
- 株式は存在しないため「株式譲渡」は不可
- 主な承継手法は「事業譲渡」
- 解散時の残余財産は法人の定款に基づき帰属先を決定(社会福祉法人より自由度が高い)
NPO法人が運営する保育園は、比較的小規模かつ地域に密着した事業形態であることが多いため、事業単位での柔軟な買収・承継が可能です。
ただし、自治体との助成契約が継続されるかどうかや、職員の雇用条件など、承継後の行政調整には慎重な対応が求められるでしょう。
保育の現場や制度に詳しくない方でもご安心ください。ネクストビートでは、「保育への思いを持つ事業者様」の第一歩を、制度設計や現場理解を含めてしっかりとサポートします。保育園の買収・承継について聞いてみる
保育園M&Aに関する制度・行政手続き
 ponta1414 / stock.adobe.com
ponta1414 / stock.adobe.com
保育園の買収・承継においては、企業間のM&Aとは異なり、自治体や内閣府などの所管機関による許認可の継続性や行政手続きが密接に関係します。
これにあたって、園に対する「認可の有無」について把握しておく必要があるでしょう。
保育園は大きく分けて、認可保育園と認可外保育園の2種類があります。
認可保育園は、国や自治体が定めた人員配置・施設基準・保育内容を満たし、行政から認可を受けた施設です。
一方、認可外保育園は、認可を受けていない民間の施設で、基準や運営形態は多様ですが、柔軟な保育時間や独自のサービスを提供しているケースもあります。
この2つの類型は、買収・承継時に必要となる行政手続きにも大きな違いがあるため、それぞれの特徴を踏まえた対応が求められます。
認可保育園の場合
認可保育園は、児童福祉法に基づいて国が定めたさまざまな基準をクリアしたうえで、自治体の認可を受けて運営される施設です。
認可保育園のM&Aにおいては、単なる法人の譲渡ではなく、児童福祉法に基づく認可の承継や再申請が必要となります。
認可は法人単位で付与されるため、譲渡先が別法人の場合は、新たに認可を取り直すケースが一般的です。自治体との事前協議で、保育士の継続雇用や施設・運営体制が認可基準を満たすかが審査されるでしょう。
そのため、体制変更により保育の質が下がる懸念がある場合、認可が取り消しとなる可能性もあるため注意が必要です。
認可外保育園(企業主導型保育園を含む)の場合
認可外保育園は、上記の認可を受けていない民間の施設で、企業主導型保育園やベビーホテル、託児所など多様な業態が含まれます。
これらは施設基準や職員配置に関する規定が一律ではなく、各自治体による指導監督のもとで運営されます。
このような認可外保育園とのM&Aでは、許認可の承継手続きは不要ですが、施設の形態に応じた対応が求められます。
なかでも企業主導型保育園は独自の助成制度によって運営されるため、児童育成協会への事前協議と運営法人変更申請が必須です。
また、一般的な小規模の認可外園でも、所在地の自治体への変更届出や相談が必要となるケースがあります。
いずれの場合も、保育の継続性と運営体制の維持が重要視されるようです。
保育園の買収・承継に関するよくある質問Q&A
保育園のM&Aについて知っておきたい疑問について答えます。
Q1. 保育園の価格はどう決まりますか?
実務では「簡便法」という数式での算出が多く用いられます。これはマルチプル法とも呼ばれ、収益力と保有資産をもとに評価します。
この方法で価格を割り出す場合は「営業利益 × 倍率(2~5年)+純資産」といった式になります。
ほかにDCF法(将来キャッシュフローを割引く手法)などもありますが、保育園では補助金の安定性などを踏まえ、簡便法で価格を算定するのが一般的かもしれません。
Q2. 小規模保育園・企業主導型保育園の相場は?
小規模保育園は定員6〜19人であるため、売上や利益規模が限られる分、価格も比較的抑えられる傾向がありり、500万〜2,000万円が相場のようです。
一方、企業主導型保育園は国の助成金が充実しており、安定収益が見込める場合、2,000万~3,500万円前後での取引も多く見られます。
いずれの場合も、施設の立地や人材の質によっても価格は変動します。
Q3. 保育園の立地や人材構成は価格にどう影響する?
保育園の価格には、立地条件と人材構成が大きく影響します。これは単なる施設価値だけでなく、継続的な収益を生む体制が整っているかという観点で評価されるためです。
- 駅近(徒歩10分圏内)や住宅密集地
- 待機児童数の多い市区町村
- 常勤保育士の離職率が低い
- 他園にないサービスの導入など園のブランド力が高い
特に認可園では、施設・設備に対する細かい基準はもちろん、0歳児3人につき保育士1人以上を配置しなくてはならないといった職員の配置基準が設けられています。
基準を満たさなければ認可が取り消される可能性もあるため、人材確保は価格設定の目安にとどまらず、「買収・承継の前提条件」にもなるようです。
これらの要素が揃っている園は、「リスクが低く安定収益が期待できる」と判断され割引率が下がることもあるため、結果的に価格が高くなる傾向があります。
Q4. 株式会社と社会福祉法人の買収・承継後の違いは?
株式会社が運営する保育園では、株式譲渡または事業譲渡により法人ごと取得でき、買収後も自由な経営判断ができるでしょう。
従業員の雇用契約なども法人に紐づいているため、原則としてそのまま引き継ぐことが可能でしょう。
一方、社会福祉法人が運営する保育園は非営利法人であるため、営利目的の売却や株式譲渡はできません。
このため、承継には、代表理事や理事メンバーの交代により法人の意思決定機関を実質的に引き継ぎ「理事会の掌握=実質的な経営移管」という間接的なスキームが必要になるでしょう。
また、法人の公益性維持が求められ、買収後の事業運営にも一定の制約があります。
出典:社会福祉法/e-GOV法令検索出典:経営者のための事業承継マニュアル/中小企業庁出典:こども誰でも通園制度総合支援システムポータルサイト/こども家庭庁出典:合併・事業譲渡等マニュアル/厚生労働省出典:令和6年(2024)人口動態統計月報年計(概数)の概況/厚生労働省出典:法第59条の規定により社会福祉法人が届出を行う書類等の公表について/厚生労働省出典:法人の合併について/厚生労働省
保育の未来に寄り添うM&Aをサポートします
保育園の買収・承継は、単なる施設や事業の取得ではなく、制度や人材、地域との関係性を引き継ぐプロジェクトといえるでしょう。
保育園運営だからこそできる「未来に向けて子どもたちの育ちを支援する」「地域に根差して働く保護者の不安を生まない」、そんな思いに共感できる社会貢献意識も、承継後の信頼構築や定着にも大きく影響するかもしれません。
それと同時に、企業買収とは異なり、認可区分ごとに制度や手続きも異なるため、事前に制度や現場を理解した上で進めるノウハウも今後の経営に大きく影響します。
私たちネクストビートでは、保育園M&A・事業承継の支援に特化したマッチングサービスをご用意しています。
M&Aの仲介で終わらず。事業者様が安心して運営が継続できるように、取引に必要な契約書類や書面作成の支援、弁護士や会計士などの専門家の紹介など多角的なサポートを提供しています。
長い時間をかけて保育業界に深く根ざしてきた私たちだからこそ、現場の温度感や制度の実情に即したリアルなM&A支援が可能です。
「保育園のM&Aについての不明点を相談したい」「話を聞いてみてから検討したい」という段階でも、お気軽にご相談ください。保育園M&Aについて相談したい
保育施設の採用課題へのお取組み支援
保育士バンク!からのご提案
- 人材紹介サービス
- 求人広告制作代行
- 就職・転職フェア
- 認知拡大、情報発信支援
保育施設が抱える人材確保や採用課題について、保育士バンク!の担当エージェントがしっかりとサポートいたします。
各サービスへのご質問、採用課題・経営課題についてのご相談についても受け付けております。
人材紹介&求人広告採用のお問合せはこちら
お問合せ&資料ダウンロード
採用課題・経営課題に関する個別ご相談、お問合せはこちらからお願い致します。

保育士バンク!の新着求人
お住まいの地域を選択して、最新の求人情報をチェック!

 出典:
出典:



















/campaign/0004/DZ7TWBcJ3MWmgU6JV1RVa7zbReTDn5CSzSupdV30q4TVPaApz5heM6bnqp1TJkqs)