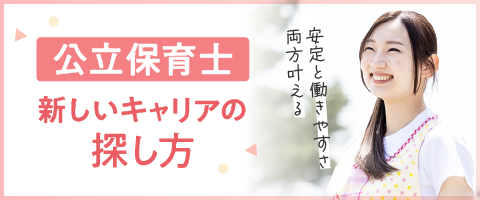「保育士」と聞くと、多くの方が保育園や幼稚園で働く姿を思い浮かべるのではないでしょうか。実は、園勤務だけではなく保育士経験を活かし、多様な働き方を実現することができます。今回は、フリーランス保育士として活動9年目を迎える「ぽっくる先生」に、フリーランス保育士という働き方の実態や、その中で見つけた保育の新たな可能性についてお話を伺いました。
園での働き方に悩みを持つ現役保育士、キャリアの岐路に立つ中堅保育士にとって、「こんな道もあるんだ」と、自身のキャリアを考えるきっかけとなるかもしれません。ぜひご覧ください。
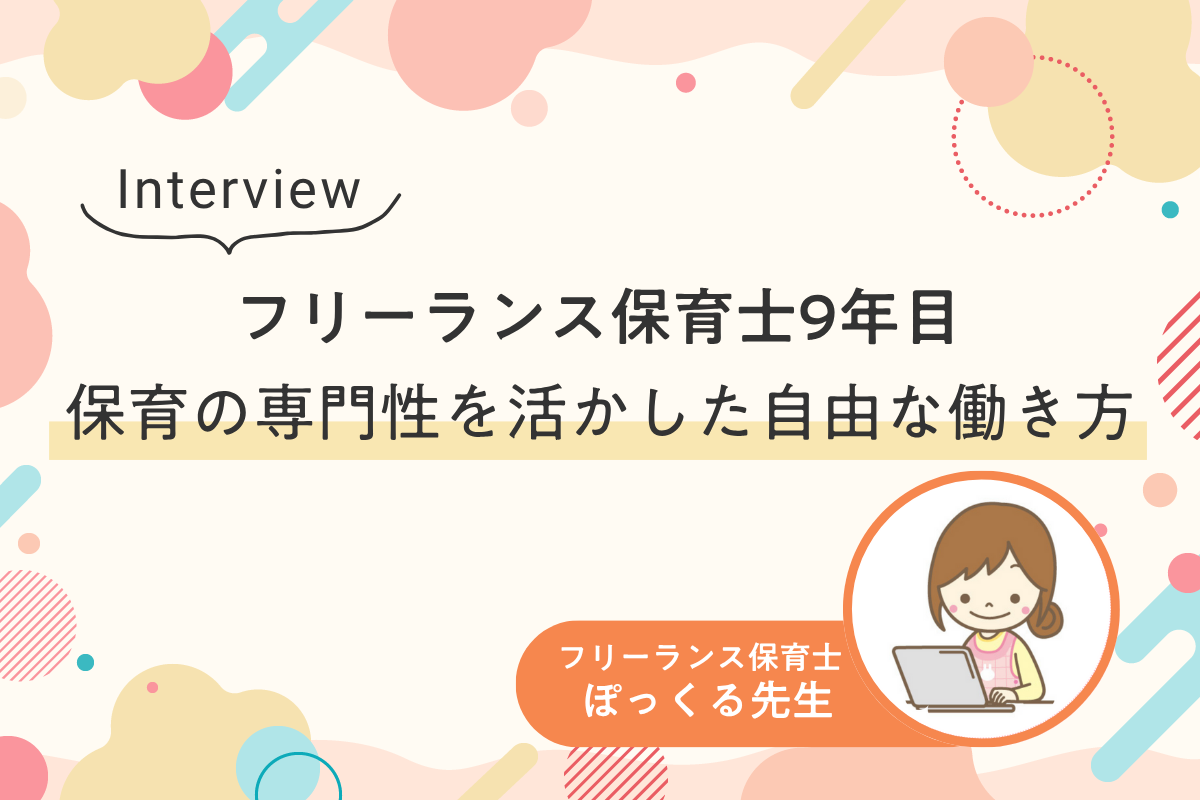
プロフィール
主な活動内容
・SNS運用、インフルエンサー活動(講座、イベント登壇)
・制作(保育系書籍、ウェブサイト、企業SNS投稿の考案・編集・撮影)
・保育教材販売(スケッチブックシアターイラスト素材などのデータ販売)
・コミュニティ運営(フリーランスを目指す保育士向けオンライン月額制コミュニティ)
・ウェブサイト運営など
経歴
4年制大学卒業後、幼稚園教諭として3年間勤務。
結婚を機に幼稚園を退職後、独学で保育士資格を取得。
認可保育園で約4年間勤務。
独立し、フリーランスとして活動開始。
フリーランス初期はベビーシッターとしても活動。
現在(2025年7月時点)は、フリーランス保育士の活動をしながら小規模保育園にも週1回、保育補助として勤務。
私がフリーランス保育士になった理由
園勤務で感じた限界と新たな道への決意
大学卒業後、私は幼稚園教諭として3年間勤務し、その後、独学で保育士資格を取得して認可保育園で約4年間働きました。
しかし、園での勤務を通して、園長や主任を目指すキャリアパスに当時の私は興味がなく、この先何十年も保育士を続けるイメージが持てませんでした。
また、保育園では両親がフルタイムで働く忙しさや、産後うつ、育児ノイローゼなど、子育てを取り巻く大変な現実に直面して、そのときに保育園の中で働いているだけでは、自分のできる支援に限界があると感じました。
この経験から、保護者支援や保育士の働く環境改善が必須だと感じ、園を離れて新たな働き方を模索するきっかけとなりました。
フリーランスへの転身と周囲の反応
独立当初は、保育士でフリーランスという働き方自体が世の中にほとんど知られておらず、前例がない中で、仕事として成り立つのか、この先どう続けていけばいいのかといった不安も大きかったです。
しかし、夫は私が保育士の仕事で大変な思いをしているのを間近で見ていたので、やりたいことがあるならと新たな道に賛成してくれました。
一方で、当時の同僚や友人からは、保育園で働かないで何をするのか、大丈夫なのかといった心配の声が多かった中で新たなキャリアをスタートしたんです。
フリーランス保育士の仕事と日々の働き方
多岐にわたる活動
私は現在、様々な活動をしています。その中心にあるのは、保育士資格を軸とした保育に関わるお仕事です。
- SNS発信や企業との連携:Instagram、YouTube、ブログなどで積極的に情報発信を行い、広告収入や企業の商品・サービスのPRを行っています。
- 講演会やセミナー開催:保育士養成校での製作に関する講演や、保育士支援センターでの働き方に関する講演、保育博などのイベントでの交流会やセミナー開催も行っています。
- 保育教材・コンテンツ制作:企業からの依頼で、保育系の書籍やウェブサイト、企業SNS投稿用の制作(考案、編集、撮影など)も行っています。また、スケッチブックシアターのイラスト素材の保育教材販売もしています。
- コミュニティ運営やイベント企画 :「保育者のセカンドキャリアを創る」をモットーに、働き方に悩んでいたり、フリーランスを目指していたりする保育士さんを対象としたオンラインコミュニティを運営し、メンバー限定のSlackでのお悩み相談やオンラインイベントを提供しています。

効率的なタスク管理術
仕事の管理では、TimeTreeで案件の締め切りや連絡先を管理し、iPhoneのメモ帳で日々のタスクリストを作成しています。
モチベーション維持のコツとしては、自身が運営するコミュニティを活用し、毎日の作業内容をメンバーに見える形で共有することです。
良い意味で自分にプレッシャーをかけて、サボれない状況を作っています。カフェで作業する際は「カフェ代を払っているから集中しよう」と自分を追い込むなど、工夫しています。

ぽっくる先生の1日のスケジュール
私は現在ほぼ在宅で、子どもが幼稚園に行っている午前9時から午後14時までを主な仕事時間としています。
忙しい時期には、預かり保育を利用したり、夫が帰宅してから夜に作業に出かけたりすることもあります。フルタイムで働くほどではないけれど、仕事と子育てのバランスが取れている今の働き方が、自分にとって最も心地よいと感じています。
|
タイムテーブル |
内容 |
|
8:30 |
幼稚園送り出し、身支度 |
|
9:00 |
カフェで仕事(コミュニティ運営業務、資料作成など) |
|
11:00 |
自宅で仕事(製作、撮影など) |
|
13:00 |
お昼休憩 |
|
13:30 |
自宅で仕事(動画編集など) |
|
14:30 |
幼稚園お迎え、買い物 |
フリーランスとしてのやりがいと挑戦
始めてみて実感したやりがい
フリーランスになって最も実感したのは、園勤務時代とは違った「やりがい」です。
保育園に勤めているときも保護者の方から感謝の言葉をいただくことはありましたが、個人で仕事をしていると、保護者の方から長文で感謝の言葉をいただいたり、SNSで繋がった保育士さんから「先生のアイデアを実際に園でやってみました」と報告があったり、ママさんから「子どもとこの遊びを家でやりました」と作った作品の画像が送られてきたりと、自分個人の存在を見てくれているような感覚があります。
そういう時は本当にやっていて良かった、誰かの力になれているんだなと感じます。
フリーランス初期にメインでやっていたベビーシッターの仕事は、保育に関わりつつ、子どもとも深く関わりながら支援ができるので、保育士として始めやすいという点でとても良かった経験です。
集団保育では一人ひとりの子どもとゆっくり関わる時間がないという悩みを抱える保育士さんも多いですが、ベビーシッターになると本当に1対1でゆったり関わることができました。

収入を確保する難しさ
フリーランスとして働く上で、収入の安定性は最も大きな課題だと感じています。特に独立当初は実績もなく、どのような仕事で生計を立てていけるか不透明だったため、一時的に収入が落ちた時期もありました。
しかし、8年間フリーランスとして活動を続ける中で、仕事の単価やニーズを感覚として掴み、経験を元に仕事を組み替えることで、現在は安定した収入を得ています。
稼働時間は保育園勤務時代よりも大幅に減っているにもかかわらず、収入は上回っています。
保育士資格を活かす“保育園以外のキャリア”
保育士資格は最強の資格
保育士資格は本当に取得してよかったと感じています。幼稚園教諭のときは主に3歳以上の子どもを見ていましたが、保育士になってからは0歳、1歳、2歳といった乳幼児期の育ちから見ることができ、知識や経験の幅が広がりました。
保育士は園の中での子どもの姿しか見ていないことも多いですが、育児を経験してみて痛感するのは、保育と育児は全く別世界だということです。育児経験がなかったとしても、家庭での様子や保護者への支援に関連する知識を学ぶことで、保護者への寄り添い方が全く違ってくると感じています。
私自身、保育園での勤務経験は、今のフリーランスの仕事の全ての大元です。保育園勤務を経験したからこそ、保育のつまずく部分や悩みに共感でき、悩みに寄り添ったアイデアなどを発信できると思います。
フリーランスに向いている人の特徴
フリーランスに向いている人の特徴として、「変化を楽しめる方」や「自分で動いていける人」だと思います。
保育園では日々の業務をこなすことで給料がもらえますが、フリーランスは自分で何を仕事にするかを考え、動かなければ収入はゼロになることもあります。
しかし、様々な人との出会いや新しい仕事内容の変化を楽しめる人にとっては、非常に向いている働き方だと思います。
保育士資格を活かせる選択肢は園以外にも。キャリアはもっと自由でいい
ぽっくる先生がこれからチャレンジしたいこと
私の活動の軸は、一貫して「子どものためになる活動」です。
保育士さんは、子どもと日中長い時間を過ごす職業だからこそ、子どもたちがより良い環境で育つためには保育士さんへの支援や保育業界の改善は必須だと考えています。
だから今はそこに力を入れています。今後も子ども、保育士さんのためになる活動であれば、できること、チャンスがあることなら何でもやっていきたいと思っています。
キャリア選択に迷う保育士さんへ
全国的に見ると、フリーランスの知名度はまだまだ低く、保育園でしか働く選択肢がないと考えている方がとても多いと感じています。
保育の仕事はしたいけれど、保育園ではないなと感じた時に、どういう選択肢があるのか、どういう働き方があるのかをまず知るだけでも、今後のキャリアは大きく変わってくるかもしれません。
もし今いる場所が合わないと感じて、逃げたいと感じているなら、一旦逃げてやってみたらいいと思います。嫌でも現実に直面することもありますが、そこで「自分は今までいかに恵まれた環境にいたんだろう」と気づくこともできるかもしれません。
あるいは、最初は逃げてきたけれど、やってみたらめちゃくちゃ向いていた、と意外と続くかもしれません。保育士という専門職の世界は、一度別の道を歩んだとしても、再び戻りやすい世界でもあります。挑戦する気持ちがあるなら、一度やってみる価値はあります。迷っているならぜひ一歩踏み出してみてください。