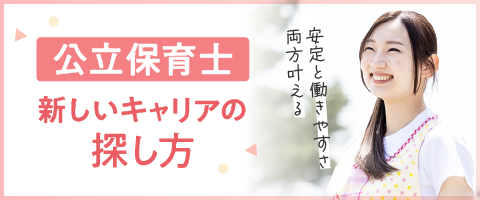保育士として、日本を離れてマサチューセッツ州·ボストンで働くことを選んだmoeさん。現在は、現地の保育園に勤務しながら、自分らしい働き方や子どもとの向き合い方を日々模索しています。保育の現場で当たり前とされていることが、場所や文化が変わるとまったく異なることもあります。ですがそれは、「どちらも正しい」ではなく、「どちらにも意味がある」こと。大切なのは、多様な働き方·キャリアを知ることで「どんな働き方が自分に合っているのか」を、自分の視点で選べるようになることではないでしょうか。今回は、ボストンで保育士として活躍しているmoeさんのこれまでの経験、リアルな保育の様子をお届けします。今の働き方に悩むすべての保育士さんにとって、自分らしいキャリアを考えるための新たな「視点」を見つけるきっかけになるはずです。
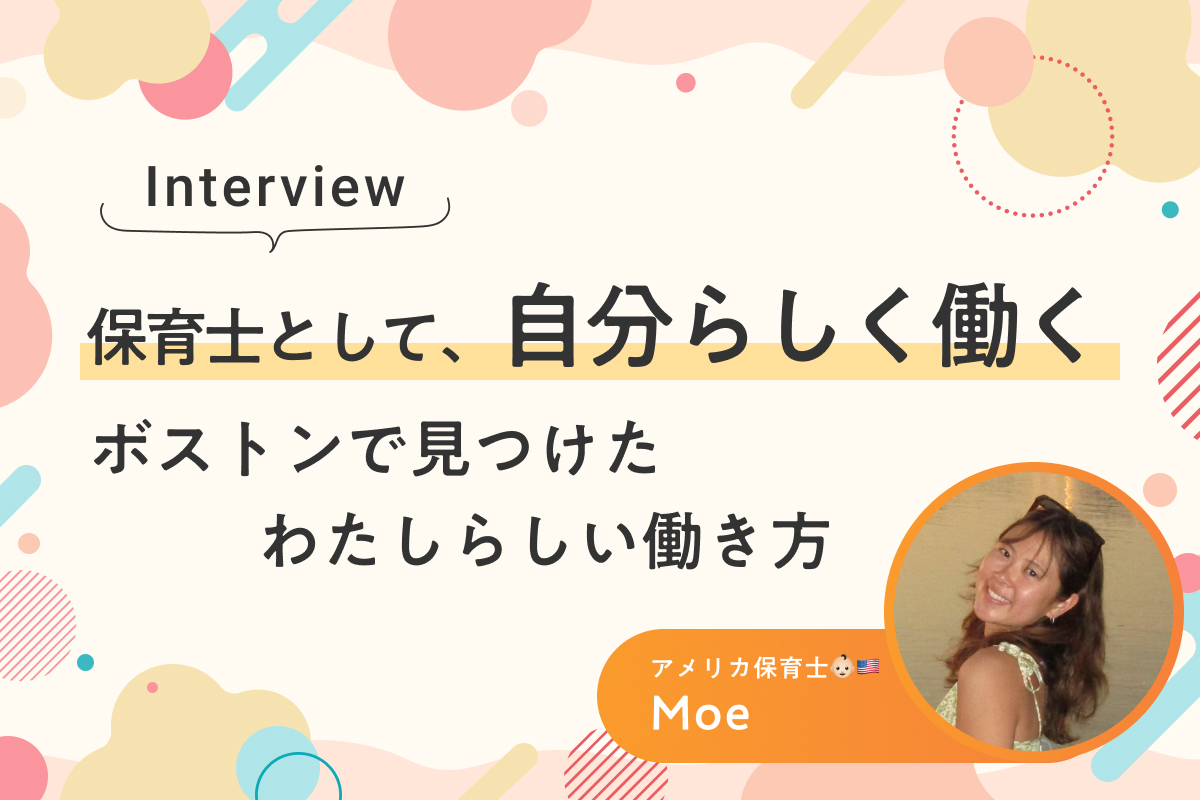
プロフィール
Moeさん(アメリカ合衆国・マサチューセッツ州ボストン在住)
職業:保育士・ベビーシッター
その他の活動:英会話レッスン運営
Instagramフォロワー:約11万人
Tiktokフォロワー:12万人
YouTubeチャンネル登録数:1.65万人
※2025年7月時点
経歴
2021年:大学在学中に渡米、マサチューセッツ州ボストンのバイリンガルスクールで保育士として勤務
2022年:現在の保育園に転職し、SNS運営も並行しながら活躍中
大学在学中にボストンで保育士としてのキャリアをスタート

もともと、私には「これがやりたい」という明確なものがありませんでした。周りが就活をしているから私もやらなきゃ、というプレッシャーや空気感の中で始めたのが正直なところです。
でも、いざ始めてみるとなんでみんなが同じ服を着て、髪の毛を黒く染めて、同じ格好で戦いに行かないといけないんだろう、と疑問が出てきました。
ちょうどその頃、アイルランド留学から帰ってきたばかりで、留学中に出会った友人から、アメリカのリアルな話を聞くうちに、ぼんやりと「アメリカで働きたいな」という気持ちが芽生えていました。
でも、当時の私は文学部で、保育とは全く無縁。じゃあ、自分は何がしたいんだろう?と考えたとき、姪っ子と遊ぶのがすごく好きで、「学生より長い社会人生活、やるなら楽しいと思えることをしたい。これを仕事にしたら、毎日楽しいかもしれない」と思ったんです。
本当にそれくらいの、シンプルな気持ちで「よし、アメリカで保育士をやってみよう」と決意しました。そこで初めて、アメリカで保育をするということが自分の中の選択肢として出てきました。
日本とアメリカと離れた場所で行う就職活動
日本にいながらアメリカの仕事先を見つけるのは、手探りでした。初めての一人暮らしが海外になる不安もあったので、まずは「日本人がいる環境」「治安のいい場所」という2つの条件を決めました。
そこから、とにかくネットでアメリカ全土のバイリンガルスクールや日本語学校を洗い出して、一園一園に直接メールを送りました。直接送ることでレスポンスも早いですし、確実に園の方に思いが届くと考えたんです。
メールを送る際には、日本の履歴書にあたる「レジュメ」を添付して、「アメリカで保育士をやりたいです。私はこういう人間です」という自己紹介も添えました。
そこからは、興味を持ってくれた園から返信が来て、オンラインで面接、という流れです。その中で採用してくださったのが、ボストンにあったバイリンガルスクールでした。
言語・文化の壁を超えて、自分の価値を伝える就職活動
面接は、園長先生が日本人の方だったので8割は日本語でした。もちろん「なぜ保育士に?」「なぜこの園を?」といったことは聞かれましたが、スキル面でピアノが弾けるか、といった質問は一切ありませんでしたね。
経験がないことについては、もちろんよい印象ではなかったと思います。でも、後から園長先生に聞いた話では、私がずっとバスケットボールを本気でやっていた経歴を見て、「この子なら辛抱強いだろうし、何があっても生き延びていくだろう」と感じてくれたそうです。
採用面接で意識した「自分を雇用することによるメリットの伝え方」
経験がない分、自分の思いを正直に伝えることを意識しました。
とにかく「経験はないけれど、人とコミュニケーションを取ることがものすごく好きだ」ということを伝えました。仕事だからとか、やらなきゃいけないからじゃなく、大人でも子どもでも、年齢を問わずに人と話をすることが好きなので、それをプロフェッショナルとしてやりたい、と。
もう一つ伝えたのは「日本人として、日本の言語や文化の素晴らしさを、アメリカに住む子どもたちに広めていきたい」という思いです。
留学経験を通して、日本語がいかに丁寧で美しい言語か、言葉のニュアンスから相手の気持ちを汲み取る文化がいかに素晴らしいかを実感していました。そうした思いを、自分の言葉で伝えていました。
ボストンで働く保育のリアル

こうしてボストンでのキャリアをスタートさせた私ですが、保育の現場では、日本の常識が通用しない、数々の違いに気づくことができました。
働き方·勤務時間の違い
残業や持ち帰り仕事は一切ありません。残業は緊急時のみで、定時を過ぎて残っていると「なんでまだいるの?」と上司に言われるくらいです。
仕事とプライベートは完全に別物。「この時間でこのお金をもらう」という契約なので、時間外に働く理由はない、という考え方が徹底されています。
また、私の園には「15分休憩」という制度があり、これは理由を問わず、どの先生でも好きなタイミングで取ることができます。「自分のケアができていない人が、子どものケアはできない」という考えが根付いているんです。
心が疲れた時に「ちょっとブレイクタイムが欲しい」と伝えると、15分間部屋を離れることができ、この制度には本当に助けられています。
【moeさんの1日のスケジュール】
|
タイムテーブル |
内容 |
|
6:00 |
起床 |
|
8:00 |
朝の準備·移動・オンライン英会話講師の仕事 |
|
9:30 |
勤務開始 |
|
9:30~10:30 |
外遊びの見守り |
|
10:30~11:20 |
室内体育館遊び |
|
11:20~11:45 |
行事に触れる時間の活動参加(サークルタイム) |
|
11:45~13:00 |
お昼ご飯の補助・お昼寝準備 |
|
13:00~15:15 |
お昼休憩 |
|
15:15~16:00 |
午後のおやつ補助 |
|
16:00~18:00 |
自由遊び・子どもたちの見送り |
|
18:00 |
退勤 |
|
18:00~18:30 |
買い物 |
|
18:30 |
帰宅 |
|
18:30~20:00 |
夜ごはん·お風呂 |
|
20:00~22:30 |
勉強・オンライン英会話講師の仕事・SNS活動 |
|
22:30 |
就寝 |
※あくまで1日の例です。
保育士と子どもとの関わりの違い
私が主に担当しているのは、15ヶ月から2歳前後の「トドラー」と呼ばれる年齢の子どもたちです。一番大きな違いは、先生の配置人数ですね。マサチューセッツ州では基準が決められていて、トドラークラスは子ども9人に対して先生が2人というのが基本です。
今働いている園はさらに手厚く、9人に対して先生が3人体制。なので、一人ひとりにものすごく手厚いサポートができます。
たとえば、特別な配慮が必要な子がいる場合、先生の一人がその子に1対1で付き添う体制を組むことも可能です。それでも残りの先生2人で子ども8人を見られるので、クラス全体が回らなくなる、ということがありません。
外遊びでは、基本的に‶見守る”保育スタイルです。もちろんいっしょに遊ぶこともありますが、どちらかというと座って見ていたり、安全を確認したりすることが中心。ただ、子どもが滑り台に登っている時などは、必ず先生が一人近くにいないといけないというルールがあり、安全面は徹底的に守られています。
基本的には保育士は子どもたちのやりたいことを見守り、それをサポートする、という形です。おもちゃを次から次へと取り出すことも、悪いことだとは教えません。
「あれが欲しい」「これが欲しい」という気持ちに対して、「じゃあ、あれをお片付けしたらこっちで遊ぼうか」と、子どもの気持ちに寄り添いながらサポートしていきます。
製作や遊びの違い
日々の活動も、日本とは大きく異なります。ピアノを弾ける先生はほとんどいなくて、基本的に音楽はスピーカーで流します。だからピアノの実技は全く求められません。
製作活動で最も特徴的なのは、「プロセスアート」という考え方が徹底されていることです。これは、出来上がったものがどんな形であれ、その過程(プロセス)を重視するという考え方です。
たとえば、「りんごのスタンプをしよう」と活動をはじめて、子どもが絵の具をぐちゃぐちゃに混ぜて、りんごの形ではなかったとしても、それがその子の表現として「OK」なんです。先生が手伝ってお手本通りの綺麗なものを作らせることは、むしろ禁止されています。だから、誰かと比べて「上手だね」という評価をすることも一切ありません。
もちろん年齢ごとに教えていくべきことは変わります。5歳児の子どもに「筆は持って書くものだ」と教えることはあっても、筆を使って出来上がったものが全く想定していないものでも「素敵なものができたね」と肯定します。その子の表現したい気持ちを尊重するんです。
また、ボストンは多様な人種の先生や子どもたちがいるので、他国の文化や行事を学び合うことに力を入れています。
私のクラスの先生も、私(日本人)、アメリカ人、アルメニア人と国籍がバラバラ。だから、私がこいのぼりや書道を子どもたちと楽しむ日もあれば、別の先生が自国の歌を教えたり、文化を紹介したり。子どもたちは小さい頃から、自然と多様な文化に触れることができます。これは私たち自身も毎日が学びで、すごく楽しいですね。
人間関係の違い
多様なバックグラウンドを持つ方々と働くなかでは、もちろん衝突もおきます。ときには険悪なムードになることも。だからこそ私が意識していることは、「自分の意思は絶対に言葉で伝える」です。
特にネガティブな気持ちは、自分のなかだけでとどめない。喧嘩をしたいわけではないので、どうすれば伝わるかを考え、必ず相手の目を見て話します。
当時採用が決まった後、保育園側から「人手が足りないからすぐに来てほしい」と言われた時も、「大学の卒業式には絶対に出たいので、その時期に帰国させてくれるなら行きます」と、自分の譲れない思いを伝えました。そのおかげで、在学中に働きながら、無事に帰国して卒業式にも出席することができました。
後日、園長先生に「経験もないのにすごい度胸だと思ったよ。でも、それくらい自分を持っている人じゃないと、この国では生き残っていけない」と言われたこともありました。言われたことをただ受け入れるのではなく、自分の実現したいことを伝える姿勢が信頼関係に繋がると感じましたね。
これからも、ボストンで保育士として挑戦する理由

次のステップとしてこれからも学び続ける
ついこの間、クラスの責任者になれる「リードティーチャー」の資格を取り終えたところです。それと同時進行で、さらに上の園長先生クラスの「ディレクター」の資格の勉強も始めました。
幼児心理学にも興味があって、本を読んだりしています。知識の引き出しが多くて困ることはありませんから。日本人として生活していて、日本人としてのアイデンティティを持つ私だからこそできることを、保育という形で将来は何か形にできたらなと思っています。
次にステップアップするために、学び続けていきたいですね。
日本で働く保育士さんに伝えたいこと
どこまで行っても、一番大事なのは「自分の人生」だと思うんです。仕事が辛くて、プライベートの時間まで暗い気持ちになってしまうのなら、一度立ち止まって「本当にこのままでいいのかな?」と自分に問いかけてみてほしいです。
私がいるボストンだけでなく、世界には数えきれないくらいの保育の形があります。今の環境が全てではありません。自分の心に生まれたモヤモヤから目をそらさずに、向き合ってみてほしいなと思います。
誰かのお世話をする仕事は、まず自分が満たされていないとできません。自分のことをしっかりケアして、大事にしてください。周りの目を気にしてしまうこともあると思いますが、自分の人生をどう彩っていくかは、自分自身で決めるもの。皆さんが、自分にとっての正解を見つけられることを応援しています。