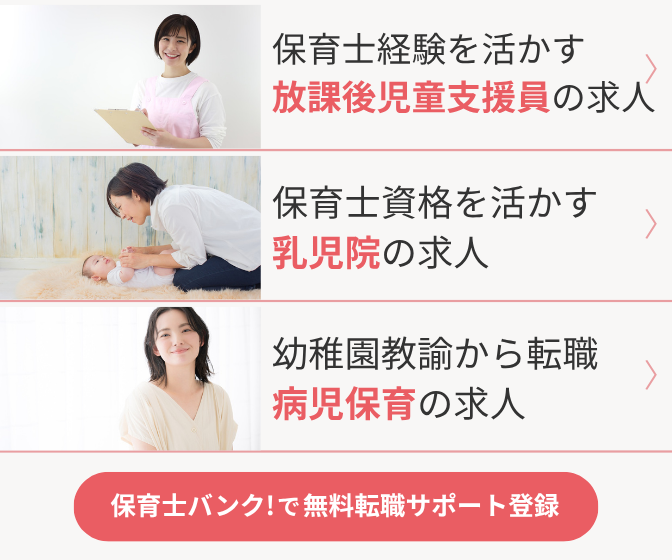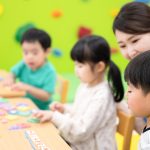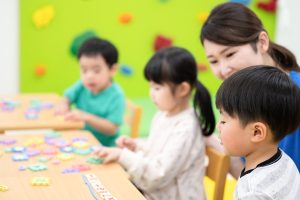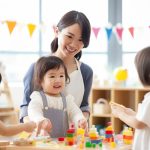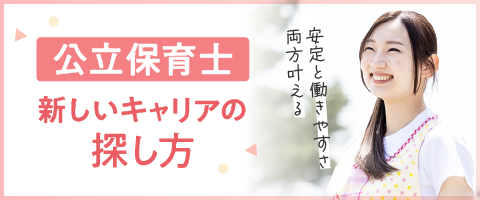「子育て支援員」は、保育や福祉の現場で子どもたちの成長を支える重要な資格です。2026年現在、放課後児童クラブや保育園では人材不足が続いており、子育て支援員のニーズはますます高まっているようです。この記事では、子育て支援員の資格とは何か、取得方法、研修内容、給料・待遇、活躍の場までわかりやすく解説します。
 polkadot / stock.adobe.com
polkadot / stock.adobe.com
子育て支援員とは
子育て支援員とは、保育人材不足の解消を目的として、2015年に子ども・子育て支援新制度によって新設された、保育の仕事に就くことができる資格です。
厚生労働省の資料「子ども・子育て支援新制度ハンドブック」によると、子育て支援員とは子ども・子育て支援の担い手にあたるとされています。
国で定めた研修を受講して子育て支援員の資格を取得することで、保育園、放課後児童クラブ、養護施設といった子育て支援の事業に必要な知識や技術を身につけたと認められるようです。
また、子育て支援員は国が定めた子どもに関わる仕事に関する資格なので、履歴書に記入することができます。就職・転職などの際には、子育て事業への意欲や知識をアピールすることにもつながりそうですね。
子育て支援員にはどのような役割があるか、詳しくみていきましょう。
子育て支援員の資格はどんな人におすすめ?
子育て支援員は、以下のような方に最適な資格と言えそうです。
- 育児経験を活かして働きたい方
- 保育士資格がないけれど、子どもに関わる仕事をしたい方
- 働きながら保育現場でのスキルを磨きたい方
保育士のような国家資格ではないため、研修は短期間で受講修了できることや、自治体によっては無料で受けられることもあるため、家事や育児、ほかの仕事と両立しながら資格を取得しやすいのも魅力です。
また、働きながら保育士や放課後児童支援の資格取得を目指している方にとっても、働きながら実務経験を積めるという点で非常に有利でしょう。
子育て支援員の役割
子育て支援員には、小規模保育園や放課後児童クラブ(学童保育)、養護施設、地域子育て支援といった子育ての拠点となる施設において、支援をサポートしていく役割があります。
地域の実情やニーズに応じた子育て支援を担うことで、子どもが成長できる環境や体制を確保することが子育て支援員に求められているようです。
保育士との違い
保育士との主な違いは、国家資格である保育士資格を取得しているかどうかです。
保育士として働くためには、保育士資格を取得している必要があります。一方、子育て支援員の資格は、地方自治体が主体となって交付する民間資格です。
そのため、保育園などで働く際には主に保育の補助業務を任されることが多いでしょう。
簡単1分登録!転職相談
保育士・幼稚園教諭・看護師・調理師など
保育関連の転職のご質問や情報収集だけでもかまいません。
まずはお気軽にご相談ください!
【子育て支援員とは】資格の取り方・なり方
 metamorworks / stock.adobe.com
metamorworks / stock.adobe.com
子育て支援員になるためには、どのような資格取得の流れがあるのでしょうか。
厚生労働省による「『子育て支援員』研修について」の資料をもとに、詳しく見ていきましょう。
資格取得の流れ
子育て支援員の資格取得に必要な研修の流れは、以下の通りです。
- 都道府県・市町村など研修の実施主体に申し込む
- 全員共通の科目となる「基本研修」を受講
- 希望のコースを選択する「専門研修」を受講
- 修了証書が発行され、子育て支援員として認定
基本研修は8時間、専門研修は短いものであれば9時間で受講ができます。保育士資格保有者は基本研修が免除されるので、さらに気軽に資格取得ができそうです。
詳しい研修の内容について、見ていきましょう。
研修内容について
子育て支援員が働く施設は、保育園から子育て支援センター、放課後児童クラブ(学童保育)など、施設形態や対象となる子どもの年齢も幅広いことが特徴です。
そのため、各施設の特徴に応じた内容を学ぶための専門研修が設けられています。
基本研修と専門研修とはどのような資格研修なのでしょうか。それぞれの内容について詳しく見ていきましょう。
基本研修
基本研修では、子育て支援の基盤を作るために、子育て支援員の持つ役割・子どもへの関わり方について学ぶことができます。
基本研修では、以下の8科目を合計8時間で学んでいきます。
- 子ども・子育て家庭の現状(60分)
- 子ども家庭福祉(60分)
- 子どもの発達(60分)
- 保育の原理(60分)
- 対人援助の価値と倫理(60分)
- 子ども虐待と社会的養護(60分)
- 子どもの障害 (60分)
- 総合演習(60分)
子育て支援に関する基礎的な知識・原理・技術・倫理を修得することで、子育て支援員としての自覚を持つことが目的となっているようです。
なお、すでに保育士資格、社会福祉士、幼稚園教諭、小学校等教諭、看護師・保健師・臨床心理技術士の資格を取得している場合は、この基本研修の受講は免除されます。
専門研修
専門研修では、子育て支援の各事業に関する特徴や専門的知識を学ぶことができます。以下の4コースから自分の希望するコースを受講することが可能です。
放課後児童コース
放課後児童クラブ(学童保育)の理解、子どもの理解のための基礎知識、子どもの育成支援、安全・安心への対応などを学ぶコースです。
放課後児童クラブ(学童保育)の放課後児童支援員を育成するための研修で、最新の子ども観や現代の子育て環境の変化などを理解できる内容のようです。
研修の所要時間は、6科目9時間です。
社会的養護コース
「社会的養護の入口」として、社会的養護の基本的理念・知識・技術を学ぶコースです。
被虐待児童など、社会的養護を必要とする子どもへの理解や対応といった、社会的養護の基本的な理解や支援技術などを学ぶことができます。
研修の所要時間は、9科目11時間です。
地域保育コース
地域保育コースでは、共通科目と「地域型保育」「一時預かり事業」「ファミリー・ サポート・ センター」の3つの選択科目を受講することができます。
共通科目では乳幼児の発達や心理、安全確保など保育に関する基本的な理念と知識を学びます。
所要時間は12科目15時間~15時間30分です。
選択科目では、いずれの科目も各事業の概要と理念・保護者対応などを学ぶことができます。科目によっては見学オリエンテーションが含まれることもあるようです。
選択科目の所要時間はそれぞれ以下の通りです。
- 地域型保育:6科目6時間~6.5時間と2日以上の見学実習
- 一時預かり事業:6科目6時間~6.5時間と2日以上の見学実習
- ファミリー・ サポート・ センター:4科目6.5時間
地域子育て支援コース
地域子育て支援では、対象となる事業形態が多様なことから、3つのカリキュラムから1つを選んで受講します。
カリキュラムの種類と所要時間は以下の通りです。
- 基本型:9科目24時間
- 特定型:5科目5.5時間(地域の実情に合わせて科目を追加する場合もあり)
- 地域子育て支援拠点事業:6科目6時間
どのカリキュラムも、各事業の概要と基本的知識を学び、事例検討などを通して理解を深めていくようです。
【子育て支援員とは】仕事内容
子育て支援員は、小規模保育施設、認可保育園、認可外保育園といった保育施設で働くことが多いようです。
ほかにも、放課後児童クラブ(学童保育)、子育て支援センター、児童養護施設といった福祉施設で働くこともできます。
なお主な活躍場所である保育園では、以下のような保育士さんのサポートにあたる仕事を任されることが多いようです。
- 午睡時間の寝かしつけ
- 昼食やおやつの食事介助
- トイレの介助
- 玩具や遊具のメンテナンスや消毒
- 保育室内や玄関などの清掃
このように子育て支援員とは、子どもと関わることから保育環境の整備にいたるまでの業務も担います。保育を裏方から支える仕事と言えるでしょう。
子育て支援員の資格を取ることで、保育や福祉、子育てに関する知識を活かして、幅広い施設や事業で活躍できそうです。
【子育て支援員とは】給料事情・待遇
 hanack / stock.adobe.com
hanack / stock.adobe.com
放課後児童クラブ(学童保育)で働く子育て支援員の給料や待遇について見ていきましょう。
地域によりますが、子育て支援員の給料はおおむね時給1,000円から1,300円程度が一般的であるようです。
時給にプラスして月5,000円程度の資格手当が出たり、資格を持っていることによって時給が100円程度上乗せされたりといった施設もあるようです。
また、子育て支援員として働く場合の待遇は、パートやアルバイトといった雇用形態が基本となるでしょう。
国が定めている保育士の配置基準によると、朝の受け入れ時間と夕方の延長保育の時間では、2人の保育士さんのうち1人を子育て支援員が担えることになっています。
そのため、保育園などでは、朝夕の時間帯を中心としたパートの募集が多いようです。子育て支援員の求人を知りたい!
【子育て支援員とは】やりがい・大変なこと
子育て支援員として保育園や放課後児童クラブ(学童保育)で働くうえでのやりがいや大変なことを見ていきましょう。
やりがい
子育て支援員のやりがいの面について紹介します。
子どもと関われる
保育士さんや放課後児童支援員さんのサポートをしながら、子どもと接することができます。
保育園では、いっしょに遊んだり、食事介助や寝かしつけたりといった身のまわりの援助を行なうことで、子どもたちとの信頼関係を深められるかもしれません。
また、放課後児童クラブ(学童保育)では、学校帰りの子どもたちの生活の場所として、学習支援や遊びをサポートしたりすることで、子どもたちの成長に関わることができるでしょう。
子どもが好きで、子どもと関わる仕事がしたいと考えている方にはメリットの一つといえるのではないでしょうか。
保育経験を積むことができる
放課後児童クラブ(学童保育)で児童支援員として勤務するためには、放課後児童支援員の資格を取得しなくてはなりませんが、資格取得には、放課後児童クラブなどの該当施設で2年から5年の勤務実績が必須要件となっています。
そのため、子育て支援員として勤務経験を積むことで、放課後児童支援員の資格取得へ挑戦することができます。
また、保育士資格を取得したいけど、実務経験がないと保育士として働き始めてからのことを不安に感じるという方もいるのではないでしょうか。
子育て支援員として子どもと関わるなかで、子どもへの理解を深めたり保育士の仕事を知ったりすることができるでしょう。
保育士資格を取得した後も、すでに子育て支援員として保育補助の経験があるため、経験値とスキルを兼ね備えた即戦力として就職・転職にも有利に働くかもしれません。
大変なこと
子育て支援員として働く際の大変なことについても知っておきましょう。
サポート業務が多い
子育て支援員とは、保育士さんや放課後児童支援員さんの業務をサポートする「補助員」としての仕事が主な役割です。
玩具の消毒や片付け、清掃といった子どもと直接関わることが少ない仕事が必然的に多くなり、大変だと感じる人もいるでしょう。
保育園などで子どもの前で絵本を読んだり手遊びをしたりといった、子どもの前に立つ仕事をイメージしていた方はギャップを感じてしまうかもしれません。
雇用の不安定さ
子育て支援員の仕事は、多くがパートやアルバイトといった非常勤雇用であるため、金銭的な不安を感じる方もいるかもしれません。
また、施設によっては保育士資格や放課後児童支援員資格を取得しても常勤になれるか不明という場合もあるでしょう。
いずれは保育士資格もしくは放課後児童支援員資格を取得しようと考えている方は、子育て支援員として働く際に、常勤への登用がある施設を探すとよさそうです。子育て支援員の求人を探したい出典:子ども・子育て支援新制度ハンドブック/厚生労働省出典:有資格者についての研修受講科目の免除について/厚生労働省出典:『子育て支援員』研修について/厚生労働省
子育て支援員の資格を取得して、保育に関わる仕事の転職に活かそう
子育て支援員の資格は、履歴書に記入することもでき、研修によって子育て支援を学んだ人材として保育園や放課後児童クラブ(学童保育)などでサポート業務を任されることが多いでしょう。
保育業界で求められる、子育て支援員の資格を取得して、育児経験を活かしながら子どもに関わる仕事を初めてみてはいかがでしょうか。
保育士バンク!では子どもと関わる仕事を多数掲載しています。
実務経験はなくて不安…だけど子育て支援員が気になる
無資格だけど子育ての経験を活かして働きたい
など、あなたの現状やご希望をヒアリングしたうえで、ぴったりの園をご紹介します。
まずは保育事務や調理スタッフとして働いてみたい!というご相談もOK♪
履歴書の添削/面接のアドバイスなど、あなたの就職・転職を徹底サポートするので、まずは登録してみてくださいね!