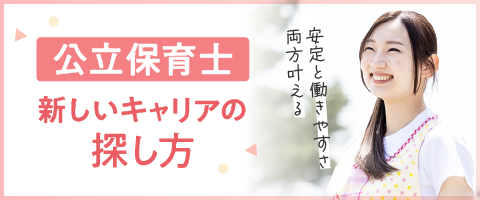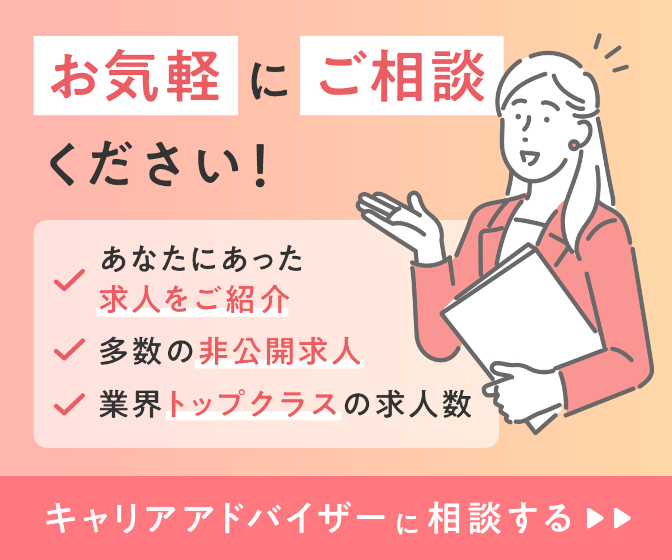こども誰でも通園制度とは、親が働いていなくても月10時間を上限に子どもを保育園に時間単位で預けられる制度です。今回は、2026年度4月から本格的に開始するため、制度の内容をわかりやすく解説!対象者や利用時間、料金から、東京都・福岡・沖縄県の実際の導入例・注意点までを詳しく紹介します。
 kimi / stock.adobe.com
kimi / stock.adobe.com
こども誰でも通園制度とは。いつから始まるの?
「こども誰でも通園制度」とは、親が働いていなくても0歳6カ月〜満3歳未満の子どもを月10時間を上限に保育園へ預けることができる通園制度です。
全国で本格的に開始されるのは「2026年度4月」。
いままで保育園は、保護者が働いていたり、病気や介護などの特別な事情があったりと保育の必要性の認定を受けた家庭のみ利用することができました。
しかし、「こども誰でも通園制度」は、保護者の就労を問わず、時間単位で「誰でも」保育園を利用できるようにつくられました。
制度内容
対象者
認可保育園、認定こども園、地域型保育事業所等に通っていない0歳6か月〜満3歳未満の子ども
利用時間
月10時間
利用料
1時間300円(園によって100円~800円前後の場合あり)
受け入れ先
保育園、幼稚園、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所、地域子育て支援拠点企業主導型保育事業所、認可外保育施設、児童発達支援センター
利用形態
・定期利用:曜日や時間を固定して継続的に通園
・柔軟利用:曜日や時間を固定せず、必要に応じて通園
※園によって利用法が異なる、上記を組み合わた提供も可能
「親子通園」も可能なため、子どもの様子や家庭の希望に合わせて、制度を利用することができるでしょう。
すべての自治体で制度が利用できますが、園の状況によっては受け入れていない場合もあります。
保育園や幼稚園に通う前の雰囲気を体験する「プレ保育」として、受け入れている場合もあります。
こども誰でも通園制度と一時預かりとの違いとは?
 buritora / stock.adobe.com
buritora / stock.adobe.com
そもそも国の一時預かり事業があるのだから、「こども誰でも通園制度」は不要なのでは?と考える保育士さんもいるでしょう。
国は以前から一時預かり事業を行ない、保護者の病気や仕事などを理由に一時的に子どもを預けられるような取り組みを実施していました。
ただ、一時預かりは基本的に保護者の病気や仕事などといった特定の理由がなければ、保育園に預けることが難しいという特徴があります。
一方、「こども誰でも通園制度」は、何らかの理由がなくても保護者が子どもを預けられることが大きく異なる点でしょう。
こども誰でも通園制度と一時預かり事業の違いは以下の通りです。
制度内容比較
| 項目 | こども誰でも通園制度 | 一時預かり事業 |
|---|---|---|
| 対象年齢 | 0歳6ヶ月〜満3歳児未満 | 病気や仕事などで家庭での保育が一時的に困難なこども |
| 利用時間 | 1カ月あたり10時間程度の上限 | 保育園や園によって異なる※市町村で上限時間や日数を設定 |
| 事業目的 | ・親が働いていなくても、各家庭のライフスタイルに合う支援 ・子ども同士で遊ぶ経験や土台作りの支援 |
・親の就労や病気などで一時的に保育が困難なときに支援 ・乳幼児に必要な保護を行う |
| 実施自治体 | すべての自治体 | 自治体全体の81.5%実施※2024年10月時点 |
※一時預かり事業では障がいのある子どもがいるご家庭に保育士が訪問し、お世話をするサービスも行っています。
こども誰でも通園制度の助成金はいくら?
子ども誰でも通園制度を導入した園には、助成金が支給されます。
0歳児:こども一人1時間あたり 1,300 円
1歳児:こども一人1時間あたり 1,100 円
2歳児:こども一人1時間あたり 900 円
2023年度より「こども誰でも通園制度」は試験的な実施を行っていました。
当初、国からの助成金は子ども一人あたり、1時間につき一律850円でした。
しかし、補助金850円に加え、保護者からの利用料金が300円だった場合は、合計で1,150円。
この金額では「運営が難しい」という声が多く寄せられ支給額が追加されました。
そのため、事業者は上記の助成金を受け取りながら運営できるため、園で体制を整えていくべきか、しっかり考えてみましょう。
「園児がなかなか集まらない」「空き教室を有効に使いたい」といった方は、こども誰でも通園制度を活用し、子どもの受け入れを考えることも大切です。
保育士・幼稚園教諭・看護師・調理師 etc.無料転職サポートに登録保育士バンク!の新着求人
お住まいの地域を選択して、最新の求人情報をチェック!
選択済みの市区町村
こども誰でも通園制度の保育方法と流れ
ここでは、こども誰でも通園制度の保育方法や3つの導入事例について詳しく見ていきましょう。
保育方法
保育方法は主に以下の3つです。保育の方法を用いて試験的に実施しています。
【一般型(在園児と合同)】
保育園などの定員に関係なく、在園児といっしょに保育を行います。保育士の配置基準を満たせば、各園で子どもの受け入れ人数を自由に設定することができます。
【一般型(専用室独立実施型)】
保育園などの定員に関係なく、在園児と別のスペースで保育を行います。保育士の配置基準やスペースが確保できれば、各園で子どもの受け入れ人数を自由に設定することができます。
【余裕活用型】
利用児童が定員に達していない場合のみ、子どもを受け入れて在園児といっしょに保育を行います。
また、保育者の人員配置基準は以下のように一時預かり事業と同じです。
<保育者の人員配置>
・0歳児3人に対して保育者1人以上配置
・1〜2歳児6人に対して保育者1人以上配置
保育者の半分は保育士の有資格者を配置し、保育士以外の方は子育て支援研修または家庭的保育者基礎研修と同等の研修を修了した方の配置が義務づけられています。
また、余裕活用型の場合は、クラス定員に対する人員配置で対応が可能です。
利用開始までの流れ
保護者の利用開始までの流れは以下の通りです。
申請から予約までは「こども誰でも通園制度総合支援システム」を利用できますが、直接自治体の窓口に申請を行う必要がある場合もあるようです。
保護者から預け先として選ばれた事業者は、初回面談を実施し、必要な持ち物や子どもの健康状態・生活リズムなどの情報を共有します。
その後、利用開始日や時間などの詳細を調整していく流れとなります。
読んでおきたいおすすめ記事

【2026年版】乳児院で働くには?必要資格と給料、保育園との違いを解説
「乳児院で働くにはどうすればいいの?」と考える保育士さん必見!乳児院は、さまざまな事情で家庭で暮らせない0歳児~2歳頃の子どもを24時間体制で養育する施設です。保育士の方は仕事内容や保育園との違いなど...

【31選】子どもと関わる仕事特集!必要な資格や保育士以外の異業種、子ども関係の仕事の魅力
子どもと関わる仕事というと保育士や幼稚園の先生を思い浮かべますが、子どもに関係する仕事は意外とたくさんあります!今回は赤ちゃんや子どもと関わる仕事31選をご紹介します。職種によって対応する子どもの年齢...

企業内保育所とは?持ち帰り仕事ゼロの理由と仕事内容のリアル!給料や選び方も解説
企業内保育所とは、主に企業の従業員の子どもを預かる施設。行事や書類業務が少なく、少人数の子どもの成長を見守りながら、やりがいを感じる保育士さん多数!認可保育園との違いを「比較表」で解説し、仕事内容や実...

託児所とは?保育園との違いや施設の種類、働くメリットや給料についてわかりやすく解説
託児所とは、さまざまな形態の認可外保育園のことを指します。主に企業内や病院で行われる小規模保育や、商業施設内に開設されている一時保育などがあたりますが、保育士さんとしては、一般的な園との違いや働きやす...

保育士の年度途中退職は「無責任」ではない!法律で守られた権利と円満退職に向けた5ステップ
「担任だから年度途中で辞められない」と自分を責めていませんか?実は、保育士の途中退職は法律で認められた正当な権利です。今回は就業規則より優先される「民法の知識」や、円満退職に向けた5ステップ、実際に年...

保育士をサポート・支える仕事特集!保育補助や事務、運営スタッフなど多様な職種を紹介
保育士のサポート役として働きたいという方はいませんか?保育補助や事務、本社勤務の運営スタッフなどさまざまな仕事があるため、保育士さんを支える仕事を一挙紹介!異業種である保育士人材のキャリアアドバイザー...

保育士を辞める!次の仕事は?キャリアを活かせるおすすめ転職先7選!転職事例も紹介
保育士を辞めたあとに次の仕事を探している方に向けて、資格や経験を活かせる仕事を紹介します。ベビーシッターなど子どもと関わる仕事はもちろん、一般企業での事務職や保育園運営会社での本社勤務といった道も選べ...

病院内保育とは?働くメリットや1日のスケジュール、一般的な保育施設との違いについて紹介!
病院内保育とは、病院や医療施設の中、または隣接する場所に設置されている保育園のことです。保育園の形態のひとつであり、省略して院内保育と呼ばれることもあります。転職を考えている保育士さんの中には、病院内...

フリーランス保育士として自分らしく働くには。働き方、収入、仕事内容からメリットまで解説
保育園から独立して働くフリーランス保育士。具体的な仕事内容や働き方、給料などが気になりますよね。今回は、特定の保育施設に勤めずに働く「フリーランス保育士」についてくわしく紹介します。あわせて、フリーラ...

保育園の調理補助に向いている人の特徴7選!きつい・覚えられないの不安を解消
保育園の調理補助は、日々の料理スキルを活かしつつ、それ以上にルールを徹底できることが求められる仕事です。家庭での料理と異なり、現場では栄養士が作成した献立や、厚生労働省が定める厳格な衛生管理基準(大量...

子どもと関わる看護師の仕事10選!保育園など病院以外で働く場所も紹介
子どもに関わる仕事がしたいと就職・転職先を探す看護師さんはいませんか?「小児科の経験を活かして保育園に転職した」「看護師の資格を活用してベビーシッターをしている」など保育現場で活躍している方はたくさん...

【2026年最新版】保育士から転職しやすい異業種13選!メリット・デメリット、資格の活かし方
保育士から異業種に転職して新たな一歩を踏み出したい!という方もいるでしょう。今の環境を変えてキャリアチェンジすることで仕事へのモチベーションがupするかもしれません。今回は保育士から異業種に転職しやす...

【保育士の意外な職場30選】一般企業・病院からフリーランスまで!珍しい求人総まとめ
保育士資格を活かして働ける意外な職場は多く、病院、一般企業、サービス業などたくさんあります!今回は、保育園以外の転職先として人気の「企業内・院内保育」から異業種の「フォトスタジオ」「保育園運営本部」ま...

【2026年最新版】幼稚園教諭免許は更新が必要?廃止や有効期限切れの場合の対処法をわかりやすく解説
幼稚園教諭免許更新制については、2022年7月1日に廃止されました。以降は多くの教員免許が「更新不要・期限なし」として扱われるようになりました。ただし、制度廃止前にすでに失効していた免許状には、再授与...

保育士が児童発達支援管理責任者(児発管)になるには?実務経験や要件、働ける場所など
保育士の実務経験を活用して目指すことができる「児童発達支援管理責任者(児発管)」について徹底解説!多くの障がい児施設で人材不足が続いているため、児童発達支援管理責任者(児発管)を募集する施設が多数!2...

幼稚園教諭からの転職先18選!資格を活かせる魅力的な仕事特集
仕事量の多さや継続して働くことへの不安などを抱え、幼稚園教諭としての働き方を見直す方はいませんか。幼稚園教諭の転職を検討中の方に向けて、経験やスキルを活かせる18の職場を紹介します。保育系の仕事から一...

【2026年最新】放課後児童支援員の給料はいくら?年代別の年収やこの先給与は上がるのかを解説
放課後児童クラブや児童館などで働く資格職「放課後児童支援員」の平均給料はいくらなのでしょうか。放課後児童クラブで働く職員は資格の有無を問わず「学童支援員」と呼ばれ、給与が低いイメージがあるようですが、...

【2026年最新】保育士の給料は本当に上がる?5.3%賃上げや「上がらない」と感じてしまう理由
「処遇改善で給料が上がるって聞いたのに、実感がない…いつ上がるの?」そんな声が保育現場から聞こえる中、政府は保育士の人件費を2025年までには10.7%、2026年には5.3%の引き上げを発表!処遇改...

私って保育士に向いていないかも。そう感じる人の7つの特徴や性格、自信を取り戻す方法
「せっかく資格を取ったのに、保育士に向いていない気がする」仕事に誠実に向き合っているからこそ、このような不安を感じてしまうものです。保育士に向いていないと感じる原因は、あなたの能力不足ではなく「職場環...

ベビーシッターとして登録するなら「キズナシッター」を選びたい理由トップ5
ベビーシッターとしてマッチングサービスに登録する際に、サイト選びに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。収入や働き方の安定性、サービスごとの特徴や魅力も気になりますよね。本記事ではそんななか「キズナ...

子育て支援センターで働くには?職員になるための資格や保育士の役割・仕事内容をわかりやすく解説!
子育て支援センターとは、育児中の保護者と子どもをサポートする地域交流の場。保育士経験者は資格を活かして働けるため、転職先のひとつとして考えることも大切です。今回は、職員になるための資格や保育士の役割、...

ベビーシッターになるには資格なしでOK!未経験から始める3つの方法と手順
共働き世帯の増加に伴い、需要が高まっているベビーシッター。ベビーシッターになるには、無資格・未経験からでもスタートできます。働き方には「マッチングサイト(個人事業主)」「派遣会社」「パート・アルバイト...

【2026年最新】子育て支援員とは?資格取得の方法・研修、仕事内容などについて解説
「子育て支援員」は、保育や福祉の現場で子どもたちの成長を支える重要な資格です。2026年現在、放課後児童クラブや保育園では人材不足が続いており、子育て支援員のニーズはますます高まっているようです。この...

【2026年版】保育士の転職時期はいつ?年度途中の退職・4月入職のスケジュール
「そろそろ転職したいけれど、いつ動くのが一番いいんだろう…?」そんな不安を感じている保育士さんにとって、安心して転職を進められるベストタイミングは4月(=3月末退職)です。今回は、4月転職が最適な理由...

【2026年版】幼稚園教諭免許の更新をしていない!期限切れや休眠状態の対応、窓口などを紹介
所有する幼稚園教諭免許が期限切れになった場合の手続きの方法を知りたい方もいるでしょう。更新制の廃止も話題となりましたが、更新していない方は今後の対応方法をくわしく把握しておくことが大切です。今回は、幼...

【2026年最新】調理師の給料、年収はどれくらい?仕事内容や求人、志望動機なども徹底解説
子どもたちが毎日口にする給食やおやつを作る保育園の調理師。保育園で常勤として働く場合、年収は300万円以上が相場のようです。さらに、保育園調理師なら成長する子どもの身体づくりを助ける存在として、やりが...
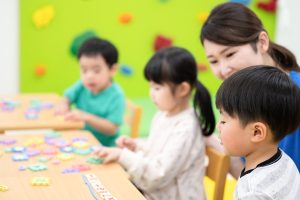
インターナショナルスクール保育士の給料相場を独自の求人データから詳しく解説
「英語を活かしたい」「年収を上げたい」と考える保育士さんにとって、インターナショナルスクール(インター)は魅力的な選択肢です。しかし、給与体系や評価基準は園によって大きく異なるため、事前の情報収集が転...

【2026年】保育士の借り上げ社宅制度とは?自己負担額と同棲・結婚後の条件を解説
保育士さんの家賃負担を軽減する「借り上げ社宅制度」。2025年度の制度改正で利用条件が変わり「制度がなくなる?いつまで使える?」「結婚してもOK?」といった疑問や不安も多いようです。本記事では、制度の...

児童館職員になるには?必要な資格やなり方、仕事内容や給料を解説
児童館職員になるには、無資格でも問題ありませんが、保育士や教員免許などの資格を持っているとさらに有利です。地域の子どもたちへの遊び場の提供や育児相談などを行う児童館、その職員について解説します。放課後...

病児保育の仕事内容とは?必要資格や1日の流れ、給料、働くメリット&デメリット
病児保育士とは、風邪などの病中や回復期で集団生活が難しい子どもを専門に預かる保育士です。保護者のピンチを支える施設別の仕事内容やスケジュールを現場の動画を交えて紹介!給料事情や感染リスク等のリアルな体...

【2026年度】保育士の給料と年収の今後は?5.3%賃上げと処遇改善の仕組み
2026年度、保育士の給与は5.3%の追加引き上げが決定しました。正社員の平均年収は約407万円、パート時給は1,370円へと改善しています。しかし、国からの手当は園を経由して配分されるため、「手取り...

保育園の事務仕事がきつい理由TOP5!仕事内容や給料、業務で楽しいと感じることも紹介
保育園で事務職の仕事を知りたい方必見!仕事に就いてから後悔しないように、今回は、保育園事務の仕事内容や業務がきつい理由・楽しいと感じることTOP5をわかりやすく紹介します。給料や待遇、採用に向けた面接...

新生児介護職員として無資格で働くには?病院や乳児院などでの仕事について
新生児介護職員など、新生児のケアに携わる仕事に関心を持つ方には、無資格でも働けるのか気になる方がいるかもしれません。基本的に「新生児介護職員」という職種はありませんが、新生児のケアに関わる仕事を指すこ...

病児保育士になるには資格が必要?未経験からのルート・給料・職場診断も公開
病児保育士は、保育士資格があれば未経験からでも挑戦できる働き方のひとつ。現場で役立つ認定病児保育スペシャリストなどの民間資格、気になる給料事情を徹底解説。さらに、自分に合う職場がわかる診断や病児保育室...

乳児院とは?果たす役割や子どもの年齢、現状と今後の課題など
乳児院とは、なんらかの理由で保護者との生活が困難な乳児を預かる施設です。一時保護やショートステイで滞在する場合もあり、保育士の求人もあります。そんな乳児院とはどんな施設なのか、厚生労働省の資料をもとに...

新しい働き方「総合職保育士」とは?仕事内容や働くメリット、給料事情など
総合職保育士という働き方をご存じでしょうか?近年注目されはじめている新しい働き方で、保育士以外の職種にキャリアを転換しやすいことが特徴です。今回は、総合職保育士について、仕事内容や給料事情、キャリアコ...

乳児院で働く職員の一日の流れは?仕事内容や年間行事、早番~夜勤の勤務時間まで
乳児院で働く職員の一日の流れや仕事内容とはどのようなものなのでしょうか。乳児院は24時間365日子どもたちを養育する施設であることから、交代制の勤務形態がほとんどです。今回は乳児院で働く職員の一日の流...

乳児院の給料はいくら?職員の資格別に平均給与を確認しておこう
乳児院は乳幼児期に適切な養育が受けられない乳児を保護し、健全な育成を図るための施設であり、医師や看護師、保育士などさまざまな資格を持つ職員が働いています。そんな乳児院の給料事情について、詳しく知りたい...

乳児院でボランティアとして活動したい!活動内容やボランティアを探す方法を紹介
乳児院は乳幼児期に適切な養育が受けられない乳児を保護し、健全な育成を図るための施設です。社会的に大きな意義のある施設だからこそ、その力になりたいとボランティアとしての活動を希望する場合もあるでしょう。...

保育士さんが乳児院を辞めたい理由。働き方や悩み、ひどいと感じる時とは
乳児院で働く保育士さんが辞めたいと感じるのはどんなときでしょうか。勤務体制、保育の内容などさまざまな問題で、ひどい・つらいと思うことがあるかもしれません。また、保育をする上で乳児院ならではの難しさもあ...

乳児院で働く看護師とは。役割や仕事内容、給料事情など
看護師資格を活かして働ける転職先の一つとして、乳児院を検討している方もいるかもしれません。しかし、そもそもどんな施設で、病院や保育園での仕事内容とどう違うのかなど気になりますよね。今回は、乳児院で働く...

保育において欠かせない養護とは?乳児期と幼児期のねらい
保育における養護は、子どもたちの健康管理を担うという役割だけではなく、子どもたちの心身の健やかな成長を支えるという大切な要素も含まれています。けれども、具体的な内容や対応の仕方について戸惑う方も多いの...

保育園における乳児保育について知っておこう。概要や保育士さんの役割
保育園で行なう乳児保育とは、どういったものなのでしょうか。乳児保育に興味を持っていながら、自分に向いているのか気になっている人もいるでしょう。今回は、保育園における乳児保育について、概要や保育士さんの...

乳児保育に興味がある保育士さん必見!やりがいや大変なこと
乳児保育に興味があるという保育士さんもいるのではないでしょうか。乳児保育とはどのようなものなのか特徴などをおさえておくと、就活の際に役立つかもしれません。今回は乳児保育を担当する保育士さんが感じる、や...

乳児向けのふれあい遊び。ねらいや効果、保育園で楽しめる人気の手遊び歌
乳児クラスでのコミュニケーションにぴったりなふれあい遊び。0歳児や1歳児、2歳児の子どもたちは、保育士さんとスキンシップを取りながら、わらべうたや手遊び歌を楽しんでくれるかもしれません。今回は、保育園...

【35選】乳児向けの室内遊びまとめ。保育のねらいや、ゲーム・製作など春夏秋冬のアイデア
雨の日や冬の寒い日、夏の日差しの強い日などは、保育園で乳児さんと室内遊びを楽しみましょう。今回は乳児(0歳児・1歳児・2歳児)クラスで楽しめる運動やゲーム性のある遊び、製作遊びのアイデア35選を紹介し...

保育士に人気の乳児保育。0~2歳児の赤ちゃんとの接し方や、働く上での魅力とは?
0~2歳児の赤ちゃんのみを対象とした乳児のみの保育園、なかでも小規模保育が、ここ数年で驚くほど増加しているのはご存じでしょうか?2017年3月の時点で設置数は2,553件。ここ2年間で約1.5倍ほど増...

乳児保育の現場での子どもの名前を呼ぶねらいとは?名前を覚えるための遊びも紹介
乳児保育の現場で、日常的に子どもの名前を呼びますが、そこには子どもの安心感を育み、信頼関係を築くための重要な役割が込められています。そもそも名前を呼ぶという行為は、子どもにどのような影響を与えるのでし...

資格なしで新生児ケアアシスタントとして働くには?新生児ケアに携わるために知っておきたいこと
保育関係の資格なしでも「新生児ケアアシスタント」という仕事に興味を持つ方がいるかもしれません。新生児ケアに関わる職種はさまざまありますが、実際には資格が必要な職種が多いのが現状です。今回は、資格なしで...

認定病児保育専門士になりたい!資格の取り方や役割など
病児保育における専門的な知識を持つ認定病児保育専門士。この資格を取得することで、保育士としてのキャリアが広がり、病児・病後児保育室などの活躍の場が一層増えるでしょう。この記事では、認定病児保育専門士の...

認定病児保育スペシャリストの資格の活かし方!就職に有利な仕事は?
認定病児保育スペシャリストの資格を活かして働きたいと考えている保育士さんもいるでしょう。保育士として、資格で得た知識を使える場面もあるかもしれません。今回は、認定病児保育スペシャリストの資格を持ってい...

【例文あり】病児保育士に転職したい!志望動機の書き方や働くメリットなど
発熱や病気で、保育園に登園できない子をスポットで預かるのが「病児保育施設」です。そんな病児保育士へ転職したい!でも、どうアピールすればよい?と、志望動機でつまずく保育士さんもいるようです。今回は、病児...

職場としての認定こども園の種類、保育士の働きやすさ
「認定こども園」とは、保育所と幼稚園それぞれの良さを生かした施設のことです。なんとなく知っていても、具体的な定義や仕事内容まで説明できる保育士さんは少ないのではないでしょうか?今回のコラムでは、認定こ...
- 同じカテゴリの記事一覧へ
【地域別】「こども誰でも通園制度」導入事例
子ども誰でも通園制度は、園の受け入れ体制が整わなければ、運営が難しいという場合もありますが、園の体制に合わせて無理のない範囲で実施している園も多いようです。
ここからは、こども家庭庁が公表した「子ども誰でも通園制度の事例集」をもとに、試行事業に参加した保育園や幼稚園について、詳しく紹介します。
東京都の幼稚園
施設概要
- 開所曜日月・火・水・木・金
- 開所時間8時30分~16時30分
- 利用可能時間10時間超
- 定員12名/1時間
- 対象年齢1歳半~2歳
保育のポイント「充実した幼児教育の提供」
専用室で安定的な受け入れを確保し、プレ保育や満3歳児クラスの経験がある園として、保育士の有資格者を担当として配置しています。
開始時は親子通園や短時間での利用などを行い、子どもの特性に合わせて、きめ細やかな対応を大切にしています。
また、在園児といっしょに手遊びや歌、体操など楽しみながら過ごせるよう、配慮しています。
福岡県の保育園
施設概要
- 開所曜日月・水・木・金
- 開所時間8時30分~16時30分
- 利用可能時間10時間超
- 定員12名/1日
- 対象年齢0歳6か月~2歳
保育のポイント「食育に配慮した幼児教育」
子ども一人ひとりの発育に合わせた食育を大切にしています。給食の場面には保護者も立ち会ってもらい、子どもの育ちを実感できるようにしています。
離乳食の進め方や偏食、アレルギー対応についても、親子通園や事前面談を通して、保護者と連携し、丁寧にサポート。
「子どもの偏食が減った」「よく食べるようになった」との保護者からの声が届き、成果を感じています。
沖縄県の保育園
施設概要
- 開所曜日月・火・水・木・金
- 開所時間9時~17時
- 利用可能時間10時間
- 定員3名/1時間
- 対象年齢0歳6か月~2歳
保育のポイント「小規模園ならではの柔軟な通園支援と保護者連携」
一時預かり事業(一般型)を実施するうえで、地域で家庭保育をしている子育て世帯が感じる孤独感や負担感を知り、未就学児家庭への支援の必要性を感じ、試行事業に参加。
補助金を活用し、専用室を改修して在園児と交流できる空間を確保し、生活リズムの異なる子どもの受け入れを行っています。
利用者は月に3回程度の通園のため、送迎時は家庭での子どもの様子や園での活動を丁寧にコミュニケーションを取り、保護者との信頼関係の構築を大切にしています。
「こども誰でも通園制度」の子どもの受け入れ園の決まり方
 buritora / stock.adobe.com
buritora / stock.adobe.com
こども誰でも通園制度は全国すべての保育園で実施されるものではありません。
事業者側は、自治体からの認可を受けることで、受け入れを開始できます。流れは以下の通りです。
その際、以下の内容を検討する必要があります。
- 「こども誰でも通園制度」を単独で行うか、他の事業所と併設するか(一般型・余裕活用型など)
- 受け入れる子どもの年齢や時間枠を設定
- 定期利用か柔軟利用か、どの程度継続的に受け入れるかを決定
- 食事の提供の有無や、提供体制・献立作成方法を検討
- 親子通園の実施可否や回数・期間を決定
- 障害児や医療的ケア児など、特別な支援が必要な子どもの受け入れ方を検討
- その他、キャンセルポリシーや災害時対応などを考慮
これから、受け入れを検討している事業者は職員体制や環境の整備の可能かを含めて、検討することが大切でしょう。
こども誰でも通園制度で子どもの受け入れが決まった場合の注意点
子ども誰でも通園制度で受け入れ園になった場合の注意点を詳しく紹介します。
職員同士の話し合いを大切にする
月10時間を上限に子どもを預かるため、その時間内で子どもの様子を把握することに不安を抱く方もいるでしょう。
そのため、職員同士で連携を図りながらそれぞれの子どもの発達状況や様子を確認し、引継ぎをしっかり行なうことが大切になりそうです。
保育士さんがスムーズに引継ぎできるよう、園側も体制をしっかり整えることがポイントになりますね。
体調管理に気をつける
なかには、人員配置が変わり、こども誰でも通園制度による子どもの預かり担当となることで、変化に馴染めずに体調を崩す保育士さんもいるかもしれません。
環境の改善を求めてもなかなか働きやすい状況にならない場合は、転職を検討してみてもよいでしょう。
そんなときは自分らしく保育士を続けるにはどうしたらよいのか、どんな園が自分に合っているのか、改めて考えてみるとよいですね。
会員登録・相談無料保育士バンク!で転職相談保育士資格を活かす転職先を探している方はいませんか?以下の記事でどのような職場があるかチェックしてみてくださいね。
こども誰でも通園制度について詳しく知ろう
こども誰でも通園制度は、子育て家庭の支援を強化するうえで重要な施策のひとつでしょう。
ただ、預かる側である保育園の職場環境が整っていることが大切になります。
処遇改善などによる保育士の労働環境の見直しが進められていますが、現在すでに今の職場環境に対して不満がある方は、将来的な自分の理想の働き方について考えてみましょう。
「もっと働きやすい園へ転職したい」「職員数が多い園で働きたい」といった希望がある方は保育士バンク!までご相談ください。
あなたが保育士としてやりがいをもって働ける職場を保育士転職専門アドバイザーといっしょに探していきましょう。
出典:こども誰でも通園制度の実施に関する手引/こども家庭庁出典:13.一時預かり事業の実施率/こども家庭庁出典:こども誰でも通園制度/こども家庭庁出典:こども誰でも通園制度(仮称)の創設について/こども家庭庁出典:乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の実施について/こども家庭庁出典:こども誰でも通園制度事例集/こども家庭庁
保育士バンク!の新着求人
お住まいの地域を選択して、最新の求人情報をチェック!


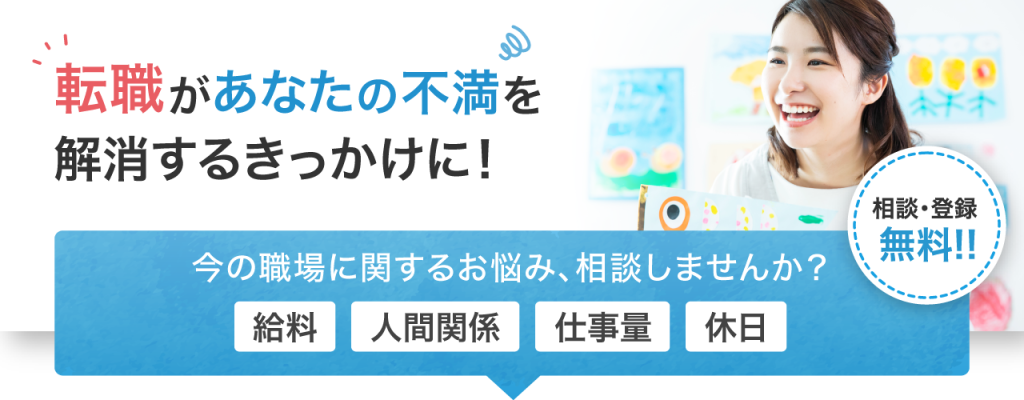





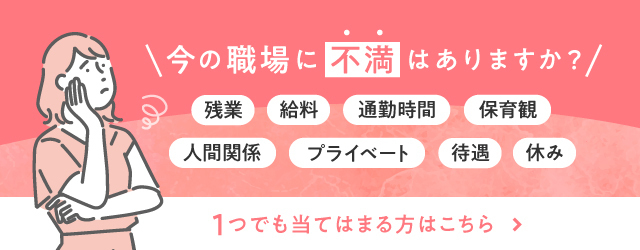
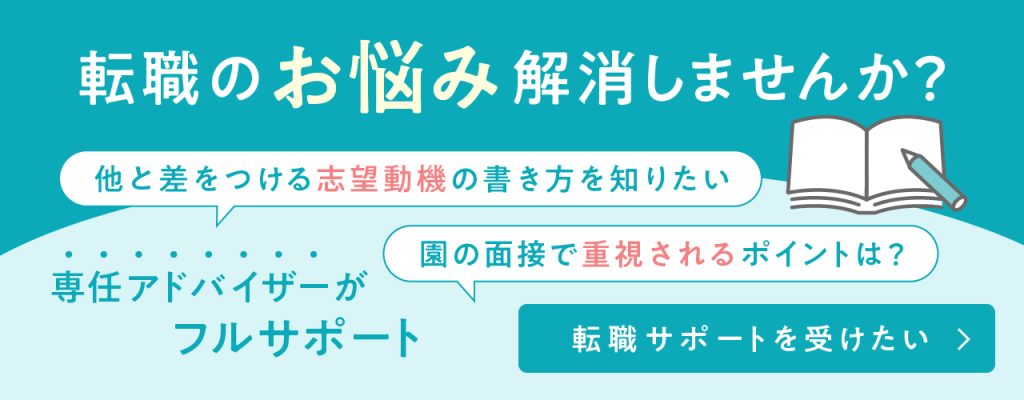
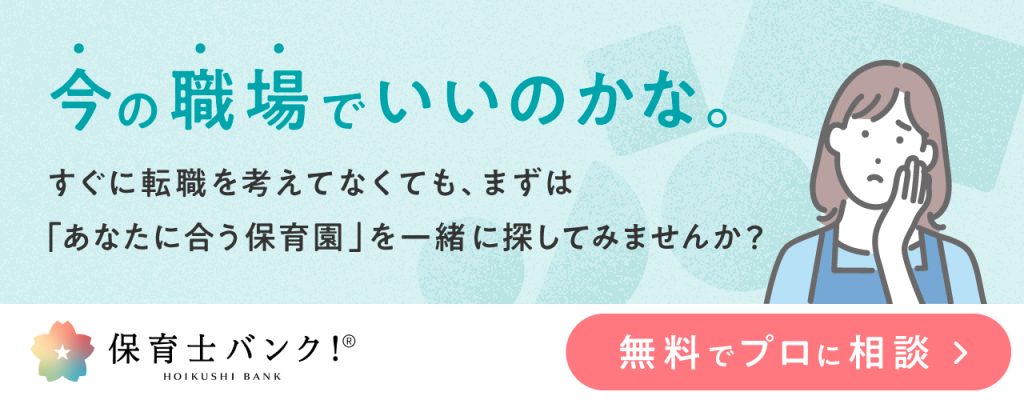
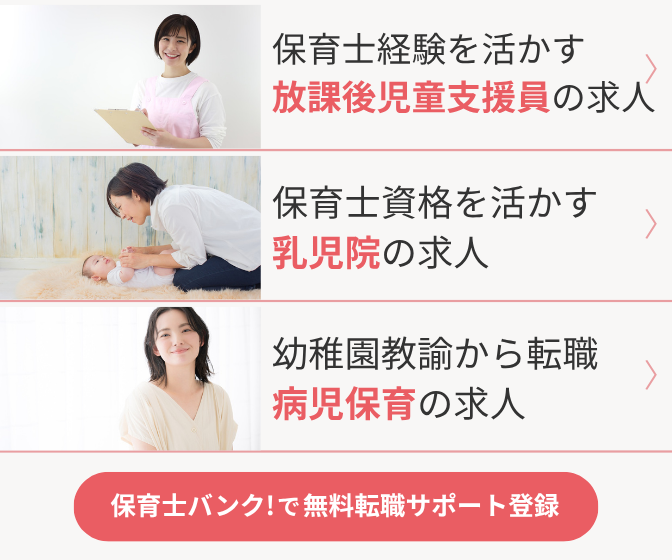

























/campaign/0004/DZ7TWBcJ3MWmgU6JV1RVa7zbReTDn5CSzSupdV30q4TVPaApz5heM6bnqp1TJkqs)