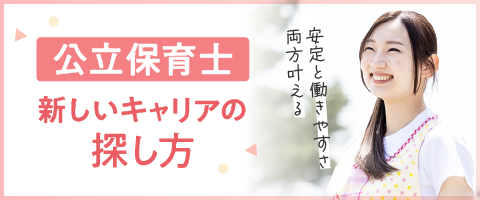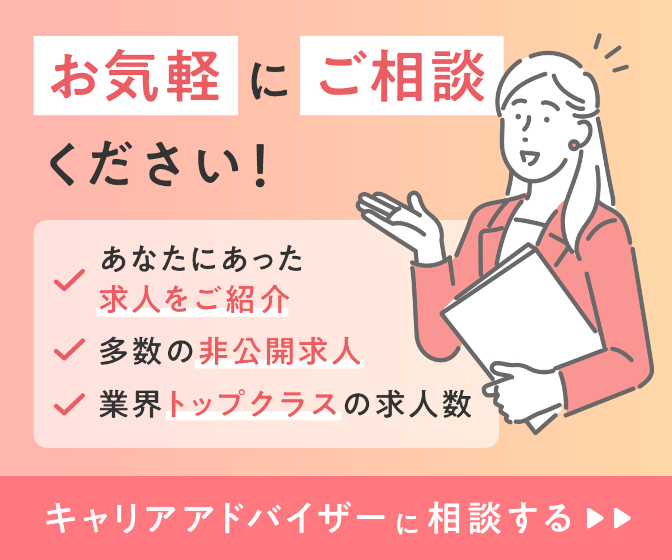保育士を目指す社会人にとって、最短で資格を取得する方法は「保育士試験ルート」への挑戦。一方で、夜間や通信で通える短大・専門学校などに通学して資格を取る「養成校ルート」も選択肢のひとつ。働きながら資格を取得した方の体験談や通学・通信での学習スケジュール例、費用をおさえるコツまで、実践的な情報が満載。夢の実現にお役立てください。
 milatas / stock.adobe.com
milatas / stock.adobe.com
社会人が「保育士」を目指すのは難しい?働きながら夢を叶えた体験談
「今から保育士を目指しても遅くないかな?」「仕事と両立できるか不安…」
そんな迷いを抱きながらも、保育の道に進もうか悩んでいる方はいませんか?
まずは、通学や通信講座を活用して資格を取得した社会人の方の体験談を見ていきましょう。
実際にどんな風に仕事と両立しながら保育士資格を取ることができたのか、参考にしてみてくださいね。
働きながら夜間大学に通学して保育士資格を取得!
通信講座で保育士試験に合格!5カ月で資格を取得
このように、社会人になってからでも、保育士を目指す方法は一つではありません。
上記の体験談のように、自分に合った方法を見つけて保育士資格を取得した社会人の方はたくさんいます。
大切なのは、「保育士になりたい」という気持ちを信じて、一歩踏み出すことです。
社会人から保育士になる!保育士試験・養成校通学ルートのメリット&デメリット
 west_photo / stock.adobe.com
west_photo / stock.adobe.com
社会人から保育士を目指すには、大きくわけて「保育士試験に合格するルート」と「養成校へ通学して卒業するルート」の2つがあります。
また、養成校への通学ルートを検討する社会人の多くは、夜間部や通信制を中心に進学先を選んでいます。
ここでは、それぞれのルートの特徴や学び方の違い、メリット・デメリットについて詳しく紹介します。
学習期間や費用などに大きな違いがあるため、これから保育士を目指す方はどちらを選択するべきかをしっかり考えましょう。
【最短5カ月】保育士試験ルート
社会人や主婦の方に人気の「保育士試験ルート」。
保育士試験は、全国で毎年2回、主に【前期:4月〜6月】【後期:10月〜12月】に実施されています。
在宅で学習し、試験の合格を目指すため、働きながら挑戦しやすいルートです。
保育士試験の内容
保育士試験の受験資格は以下の通りです。
- 大学・短期大学・専門学校の卒業者
- 1991年3月31日以前に高等学校の卒業者※2025年時点で52歳以上の方が該当
- 高校を卒業し、児童福祉施設などで所定の実務経験者(2年以上かつ2880時間以上)
- 中学校を卒業し、児童福祉施設※などで所定の実務経験者(5年以上かつ7200時間以上)
上記の条件を満たしていれば、年齢にかかわらず誰でも保育士試験を受けることができます。
保育士試験は筆記試験クリア後に実技試験を受けることで、合格を目指します。
【筆記試験の科目(全9科目)】
保育原理/教育原理および社会的養護/子ども家庭福祉/社会福祉/保育の心理学/子どもの保健/子どもの食と栄養/保育実習理論
※マークシート形式で100点中60点以上取れば合格
【実技試験】
実技試験は、「音楽」「造形」「言語」の3分野から、得意な2つを選んで受験します。
それぞれ、保育の場面を想定した課題が出され、歌唱や制作、語りなどを通じて表現力や基本的な技能が求められます。
保育士試験に受かるための費用の目安
| 学習方法 | 費用の目安 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 独学 | 約5,000〜1万円 | テキスト・問題集の購入費用 ※実技対策や学習管理はすべて自己対応 |
| 通信講座 | 約2〜8万円 | 筆記+実技対策教材/添削・模試サポート/動画講義や学習スケジュール機能 |
| 予備校・通学講座 | 約15〜30万円 | 通学型授業+模試・教材一式/講師からの直接指導/補講・フォロー体制あり |
※費用は目安です。講座内容や受講期間、サポート体制によって異なります。
独学で受験可能ですが、通信講座や予備校などを活用することで、効率よく合格を目指すことができるでしょう。
学習スタイルごとの費用例とサポート内容をまとめました。
選ぶ学習方法によって費用は異なるため、自分に合った内容と予算を見極めることが大切です。
保育士試験の合格率と一発合格の割合
2023年度の保育士試験の合格率は26.9%。
「一発合格」の割合は、一次情報によると約15%。約6〜7人に1人 が一回で合格している計算になります。
社会人の方の中には、集中して学習し、最短5カ月で筆記+実技試験に合格した方もいます!
また、筆記試験の科目ごとの合格を積み重ねる「科目合格制度」があるため、数年かけて計画的に取得することも可能です。
続いて、社会人が保育士試験ルートを選ぶメリット&デメリットを見ていきましょう。
保育士試験ルートのメリット
- 短期間で取得を目指せる
集中して学べば、1年以内の取得が可能なため、早く資格を取りたいという方にはおおすめ。 - 自宅学習が中心で時間の融通がきく
通信講座などを活用すれば、通学の必要がなく、自分のペースで学習できます。 - 学費をおさえられる
養成校を卒業するルートに比べて費用負担をおさえることが可能です。
保育士試験ルートのデメリット
- スケジュール管理が自己責任
いつまでにどれを学ぶか、自分で計画を立てて進める必要があるので不安な方は通信講座などのカリキュラムを利用するとよいでしょう。 - 実技への不安が残りやすい
ピアノや造形などの対策は独学だと難しく感じる人も。通信講座や教材選びが重要です。 - 実習経験がないまま就職活動になる場合も
試験ルートでは実習がないため、現場経験ゼロで就職活動に臨むケースもあります。無資格で働ける保育補助として現場に入るなど、実際の保育に触れる機会を自分でつくることも大切です。
【最短2年】通信制・夜間部の養成校通学ルート
「じっくり学びながら、実習も経験したい」「現場力をつけて保育士になりたい」
そんな方に選ばれているのが、保育士養成校への通学ルートです。
大学・短期大学・専門学校などの養成施設を卒業することで、国家試験を受けずに保育士資格を取得できます。
なお、幼稚園や認定こども園などで働ける幼稚園教諭1種・2種免許状も同時に取得可能な学校が多いのも特徴です。
保育士資格+幼稚園教諭免許状があることで、就職や転職の選択肢が広がるでしょう。
社会人がこのルートを選ぶ場合、夜間部や通信制が主な通学スタイルです。それぞれの特徴を確認しましょう。
通信制の養成校に通学する場合(在宅学習+年間通学5〜10日+実習20日程度)
通信制の短期大学や専門学校に通う場合、自宅学習を中心に年間5~10日のスクーリング(対面授業)と約20日間の実習を組み合わせて学ぶことが多いでしょう。
授業はオンデマンド動画や印刷教材を用いた自己学習形式が一般的で、空いた時間にマイペースで進めることができます。
学校によって違いがあるものの、レポート提出(月2~4本程度)や定期的なWebテストなどを通じて、学習の定着を図りながら進級・修了を目指します。
社会人や子育て中の方へのサポートも充実しており、働きながらでも保育士資格の取得を目指せます。
夜間部のある養成校に通学する場合(通学週5日×2年+実習20日以上)
夜間部は平日の夕方以降に授業がある通学課程で、週5日(月〜金)の通学が一般的です。
多くの学校では授業時間が18:00〜21:00頃に設定されており、約2年間で卒業・資格取得を目指します。
なかには、土・日・祝日を中心に授業を行う学校もあるようです。
対面授業だからこその実技指導やグループワークが充実しており、保育の実践力を身につけたい人に向いています。
なかにはマンツーマンのピアノ講習を受けられる学校があるため、「ピアノが苦手だけど上手になりたい」という方は検討してみるとよいでしょう。
また、保育実習は20日以上参加する必要があり、学校によっては柔軟な日程調整が可能です。
年齢層の幅広いクラスで、同じくキャリアチェンジを目指す仲間と学べるのは魅力的ですね。
通信制・夜間部の養成校を卒業するまでの費用の目安
通信制や夜間部の養成校を卒業に向けた費用の目安を確認してみましょう。
| 学習スタイル | 学習期間 | 学費の目安(総額) | 取得できる資格 |
|---|---|---|---|
| 通信制短期大学 | 約2〜3年 | 約70万〜160万円 | 保育士資格+幼稚園教諭(二種)免許状 |
| 通信制大学(4年制) | 約4年(短縮もあり) | 約100万〜180万円 | 保育士資格+幼稚園教諭(一種または二種)免許状 |
| 通信制専門学校 | 約2〜3年 | 約60万〜120万円 | 保育士資格のみ |
| 夜間部(短大・専門学校) | 約2年 | 約60万〜110万円 | 保育士資格(幼稚園教諭免許が取得できる学校もあり) |
※学費には入学金・授業料・スクーリング費・実習費などを含みます。
実際の費用は学校や学科によって異なるため、通学したい養成校が見つかった場合は、しっかり確認しましょう。
通信制・夜間部の養成校に通学するメリット
- 卒業と同時に保育士資格が取得できる
保育士試験の受験は必要なく、必要な単位と実習を修了すれば、確実に資格を得られる安心感があります。 - 実習を通して現場力が身につく
保育所や施設での実習があるため、子どもとの関わり方や保育の流れを体験しながら学べます。就職時にもアピールしやすい経験になります。 - 対面型の授業で質問しやすい
通信制・夜間部共に通学して対面形式で授業を受けられるため、講師の方などに質問しやすいでしょう。仲間と共に学べる環境のため、学習意欲を維持できることもポイントになりそうです。
通信制・夜間部の養成校に通学するデメリット
- 卒業までに時間がかかる
専門学校・短大でも最短2年、大学なら原則4年かかるため、今すぐ働きたい人には長く感じるかもしれません。 - 学費の負担が大きめ
通信制や夜間部でも、総額で60万〜180万円ほどかかる場合があり、試験ルートより費用は高めです。 - 自宅近くに養成校がない場合がある
国的に通信制や夜間部を設置している養成校は限られているため、自宅近くに学校がなく、通うことが難しいケースもあります。
このように「保育士試験に合格するルート」と「養成校へ通学して卒業するルート」について、それぞれメリット&デメリットがあります。
自分に合ったルートを選び、働きながらどのように仕事と学習を両立していくのかをイメージしてみましょう。
簡単1分登録!転職相談
保育士・幼稚園教諭・看護師・調理師など
保育関連の転職のご質問や情報収集だけでもかまいません。
まずはお気軽にご相談ください!
【保育士試験ルート】社会人から保育士になる!仕事と両立スケジュール例
保育士試験ルートを選択した場合は、試験の合格に向けて計画的に学習を進めることがポイントです。
通信講座などを活用しながら、約5カ月で筆記・実技の両方に合格するためのスケジュール例を紹介します。
5カ月で筆記+実技合格スケジュール
前期の試験で4月に筆記にクリア後、6月に実技に合格するスケジュール例です。
【スケジュール例】

スキマ時間などを活用し、コツコツ学習を継続することで、短期間で資格取得を目指せます。
また、通信講座では、実技対策では講師からのフィードバックを受けながら練習できる講座も多く、限られた期間でも効率的に力を伸ばせます。
限られた期間だからこそ、無理のないスケジュールを立てて、日々の積み重ねを大切にしていくことがポイントです。
仕事との両立~1日のスケジュール例~
仕事と両立する場合、1日あたりに確保できる学習時間の目安を把握し、平日は1〜2時間、休日は3〜4時間といったように、自分の生活スタイルに合わせて計画を立てましょう。
【スケジュール例】
| 時間帯 | スケジュール内容 |
|---|---|
| 6:00〜6:45 | 早起きして30分〜45分の学習(動画講義視聴・インプット中心)。 静かな朝の時間を活かして集中力の必要な分野に取り組む。 |
| 7:00〜8:30 | 朝の支度・通勤(移動中に音声教材や暗記カードアプリで復習)。 |
| 9:00〜17:30 | 勤務中は仕事に集中。昼休みに5〜10分だけ暗記カードで確認するのも◎。 |
| 18:00〜19:30 | 帰宅・夕食・リラックス時間。脳を休ませて夜の学習に備える。 |
| 20:00〜21:30 | 夜の学習時間(過去問演習や実技練習などアウトプット中心)。 集中力が切れやすい時間なのでこまめに休憩をはさむ。 |
| 22:00〜23:00 | 入浴・就寝準備。音声教材やアプリでの軽い復習にも活用できる。 |
仕事と両立しながらの学習は大変ですが、朝や通勤時間などを上手に活用し、自分の生活スタイルに合ったペースで進めていきましょう。
保育士バンク!の新着求人
お住まいの地域を選択して、最新の求人情報をチェック!
選択済みの市区町村
社会人から保育士になる!養成校通学ルートの仕事との両立スケジュール例
夜間部・通信制の養成校の通学を選んだ方は、必要な単位を修了し、卒業と同時に保育士資格を取得します。
仕事との両立を考えながら計画的に受講しましょう。
年間スケジュール
事前に年間スケジュールを把握し、通学日や課題提出のスケジューリング、実習期間の確保なども含めて、仕事との両立を考えることがポイントです。
【スケジュール例】
| 年次 | 時期 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 1年次 | 4月〜6月 | 入学式・履修登録・導入授業開始。保育原理・子ども家庭支援など基礎科目を中心に学ぶ。 |
| 7月〜8月 | 前期末レポート・テスト提出。夏期スクーリング(通信制)や集中講義の実施。 | |
| 9月 | 後期スタート。心理学・発達・保健など実践的な知識を深める。 | |
| 10月〜12月 | 保育内容(言語・人間関係等)の理解と模擬保育演習などを行う。 | |
| 1月〜2月 | 後期末試験・レポート対応。春季スクーリング準備(通信制の場合)。 | |
| 3月 | 実習指導の事前学習。次年度の保育実習に向けた準備期間。 | |
| 2年次 | 4月〜6月 | 応用科目の履修・保育の計画と実践指導演習。施設実習に備える。 |
| 7月〜8月 | 前期試験・施設実習(2週間〜3週間)開始。日誌記録・実習報告書の作成。 | |
| 9月 | 実習振り返りと後期履修開始。就職活動も本格化。 | |
| 10月〜11月 | 保育実習(保育所)2週間〜4週間。生活リズムと実習の両立に配慮が必要。 | |
| 12月〜2月 | 卒業試験・課題提出。保育士登録書類の準備・申請に向けた動き。 | |
| 3月 | 卒業式・修了。保育士証の取得、就職先の紹介など。 |
保育士養成課程における実習は、最低でも約20日間以上あるため、連続して平日に参加する必要があるでしょう。
そのため、社会人の方が実習に参加する場合、有給休暇の取得やシフト調整、職場への事前相談が必須となります。
実習期間は多くの場合、2〜4週間にわたり日中フルタイムでの拘束が必要となるため、仕事の「勤務調整」が重要になりそうです。
仕事との両立スケジュール例
夜間部や通信制の養成校では、1回あたりの授業はおおむね3時間程度が目安です。
なお、夜間部では平日の18時〜21時頃に授業を行うことが多いかもしれません。
また、通信制では普段は自宅で学習を進めますが、スクーリング(対面授業)では1回あたり90分〜180分程度の講義が複数コマ組まれることも少なくありません。
仕事や生活スタイルに合わせてスケジュールを立てることが大切です。
【スケジュール例】
| 時間帯 | スケジュール内容 |
|---|---|
| 6:30〜7:30 | 起床・朝の準備・朝食。短時間でできる復習や暗記学習を取り入れるのもおすすめ。 |
| 8:00〜17:00 | 日中は本業の勤務に集中。昼休みに少しだけ課題に目を通すのも◎。 |
| 17:30〜18:00 | 職場から学校、通信制の場合は自宅に移動。軽食や仮眠でエネルギーチャージ。 |
| 18:00〜21:00 | 授業(対面 or 在宅)。集中して授業に参加し、その場で理解を深める。 |
| 21:00〜22:00 | 帰宅・軽食・入浴など。学習内容の振り返りや課題メモもこの時間に。 |
| 22:30〜23:30 | 就寝準備。翌日の持ち物や授業の確認をして早めに休む。 |
夜間部の養成校に通う場合は、日中の仕事後に通学して授業を受けるため、体力面での負担もありますが、対面授業でしっかり基礎から保育の知識を身に付けられるでしょう。
一方、通信制ではオンデマンド動画やテキストを使って自分のペースで学習できるため、時間の融通が利きやすい一方、自己管理が求められそうです。
読んでおきたいおすすめ記事

【2026年版】乳児院で働くには?必要資格と給料、保育園との違いを解説
「乳児院で働くにはどうすればいいの?」と考える保育士さん必見!乳児院は、さまざまな事情で家庭で暮らせない0歳児~2歳頃の子どもを24時間体制で養育する施設です。保育士の方は仕事内容や保育園との違いなど...

子どもと関わる仕事31選!必要な資格や保育士以外の異業種、赤ちゃんや子ども関係の仕事の魅力
子どもや赤ちゃんと関わる仕事というと保育士や幼稚園の先生を思い浮かべますが、子どもに関係する仕事は意外とたくさんあります!今回は赤ちゃんや子どもと関わる仕事31選をご紹介します。職種によって対応する子...

企業内保育所とは?持ち帰り仕事ゼロの理由と仕事内容のリアル!給料や選び方も解説
企業内保育所とは、主に企業の従業員の子どもを預かる施設。行事や書類業務が少なく、少人数の子どもの成長を見守りながら、やりがいを感じる保育士さん多数!認可保育園との違いを「比較表」で解説し、仕事内容や実...

託児所とは?保育園との違いや施設の種類、働くメリットや給料についてわかりやすく解説
託児所とは、さまざまな形態の認可外保育園のことを指します。主に企業内や病院で行われる小規模保育や、商業施設内に開設されている一時保育などがあたりますが、保育士さんとしては、一般的な園との違いや働きやす...

保育士の年度途中退職は「無責任」ではない!法律で守られた権利と円満退職に向けた5ステップ
「担任だから年度途中で辞められない」と自分を責めていませんか?実は、保育士の途中退職は法律で認められた正当な権利です。今回は就業規則より優先される「民法の知識」や、円満退職に向けた5ステップ、実際に年...

保育士をサポート・支える仕事特集!保育補助や事務、運営スタッフなど多様な職種を紹介
保育士のサポート役として働きたいという方はいませんか?保育補助や事務、本社勤務の運営スタッフなどさまざまな仕事があるため、保育士さんを支える仕事を一挙紹介!異業種である保育士人材のキャリアアドバイザー...

保育士を辞める!次の仕事は?キャリアを活かせるおすすめ転職先7選!転職事例も紹介
保育士を辞めたあとに次の仕事を探している方に向けて、資格や経験を活かせる仕事を紹介します。ベビーシッターなど子どもと関わる仕事はもちろん、一般企業での事務職や保育園運営会社での本社勤務といった道も選べ...

病院内保育とは?働くメリットや1日のスケジュール、一般的な保育施設との違いについて紹介!
病院内保育とは、病院や医療施設の中、または隣接する場所に設置されている保育園のことです。保育園の形態のひとつであり、省略して院内保育と呼ばれることもあります。転職を考えている保育士さんの中には、病院内...

フリーランス保育士として自分らしく働くには。働き方、収入、仕事内容からメリットまで解説
保育園から独立して働くフリーランス保育士。具体的な仕事内容や働き方、給料などが気になりますよね。今回は、特定の保育施設に勤めずに働く「フリーランス保育士」についてくわしく紹介します。あわせて、フリーラ...

保育園の調理補助に向いてる人の特徴とは?仕事内容ややりがい・大変なこと
保育園で働く調理補助にはどのような人が向いてるのでしょうか。子どもや料理が好きなど、求められる素質を押さえて自己PRなどに活かしましょう。また、働くうえでのやりがいや大変なことなども知って、仕事への理...

子どもと関わる看護師の仕事10選!保育園など病院以外で働く場所も紹介
子どもに関わる仕事がしたいと就職・転職先を探す看護師さんはいませんか?「小児科の経験を活かして保育園に転職した」「看護師の資格を活用してベビーシッターをしている」など保育現場で活躍している方はたくさん...

保育士から転職!人気・おすすめの異業種20選。経験を活かす仕事ランキングや保育士以外の業種を紹介
保育士として働いていると、「保育士以外の仕事にチャレンジしてみたい」「異業種へ転職したい。事務・販売...保育士資格は活かせる?」などと考える方はいませんか?「保育士経験しかないけれど大丈夫?」と迷う...

【保育士の意外な職場30選】一般企業・病院からフリーランスまで!珍しい求人総まとめ
保育士資格を活かして働ける意外な職場は多く、病院、一般企業、サービス業などたくさんあります!今回は、保育園以外の転職先として人気の「企業内・院内保育」から異業種の「フォトスタジオ」「保育園運営本部」ま...

【2026年最新版】幼稚園教諭免許は更新が必要?廃止や有効期限切れの場合の対処法をわかりやすく解説
幼稚園教諭免許更新制については、2022年7月1日に廃止されました。以降は多くの教員免許が「更新不要・期限なし」として扱われるようになりました。ただし、制度廃止前にすでに失効していた免許状には、再授与...

保育士が児童発達支援管理責任者(児発管)になるには?実務経験や要件、働ける場所など
保育士の実務経験を活用して目指すことができる「児童発達支援管理責任者(児発管)」について徹底解説!多くの障がい児施設で人材不足が続いているため、児童発達支援管理責任者(児発管)を募集する施設が多数!2...

幼稚園教諭からの転職先18選!資格を活かせる魅力的な仕事特集
仕事量の多さや継続して働くことへの不安などを抱え、幼稚園教諭としての働き方を見直す方はいませんか。幼稚園教諭の転職を検討中の方に向けて、経験やスキルを活かせる18の職場を紹介します。保育系の仕事から一...

【2026年最新】放課後児童支援員の給料はいくら?年代別の年収やこの先給与は上がるのかを解説
放課後児童クラブや児童館などで働く資格職「放課後児童支援員」の平均給料はいくらなのでしょうか。放課後児童クラブで働く職員は資格の有無を問わず「学童支援員」と呼ばれ、給与が低いイメージがあるようですが、...

【2026年最新】保育士の給料は本当に上がる?正社員やパートの昇給額や「上がらない」と感じてしまう理由
「処遇改善で給料が上がるって聞いたのに、実感がない…いつ上がるの?」そんな声が、保育現場から聞こえる中、政府は保育士の人件費を10.7%引き上げるために、処遇改善制度を新たにスタート!2025年4月か...

私って保育士に向いていないかも。そう感じる人の7つの特徴や性格、自信を取り戻す方法
せっかく保育士になったのに「この仕事に向いていないのでは?」と不安を抱いてしまう方は多いようです。子どもにイライラしたり、同僚や保護者と上手くコミュニケーションが取れなかったりすると、仕事に自信が持て...

ベビーシッターとして登録するなら「キズナシッター」を選びたい理由トップ5
ベビーシッターとしてマッチングサービスに登録する際に、サイト選びに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。収入や働き方の安定性、サービスごとの特徴や魅力も気になりますよね。本記事ではそんななか「キズナ...

子育て支援センターで働くには?職員になるための資格や保育士の役割・仕事内容をわかりやすく解説!
子育て支援センターとは、育児中の保護者と子どもをサポートする地域交流の場。保育士経験者は資格を活かして働けるため、転職先のひとつとして考えることも大切です。今回は、職員になるための資格や保育士の役割、...

ベビーシッターになるには資格なしでOK!未経験から始める3つの方法と手順
共働き世帯の増加に伴い、需要が高まっているベビーシッター。ベビーシッターになるには、無資格・未経験からでもスタートできます。働き方には「マッチングサイト(個人事業主)」「派遣会社」「パート・アルバイト...

【2026年最新】子育て支援員とは?資格取得の方法・研修、仕事内容などについて解説
「子育て支援員」は、保育や福祉の現場で子どもたちの成長を支える重要な資格です。2026年現在、放課後児童クラブや保育園では人材不足が続いており、子育て支援員のニーズはますます高まっているようです。この...

【2026年版】保育士の転職時期はいつ?年度途中の退職・4月入職のスケジュール
「そろそろ転職したいけれど、いつ動くのが一番いいんだろう…?」そんな不安を感じている保育士さんにとって、安心して転職を進められるベストタイミングは4月(=3月末退職)です。今回は、4月転職が最適な理由...

【2026年版】幼稚園教諭免許の更新をしていない!期限切れや休眠状態の対応、窓口などを紹介
所有する幼稚園教諭免許が期限切れになった場合の手続きの方法を知りたい方もいるでしょう。更新制の廃止も話題となりましたが、更新していない方は今後の対応方法をくわしく把握しておくことが大切です。今回は、幼...

【2026年最新】調理師の給料、年収はどれくらい?仕事内容や求人、志望動機なども徹底解説
子どもたちが毎日口にする給食やおやつを作る保育園の調理師。保育園で常勤として働く場合、年収は300万円以上が相場のようです。さらに、保育園調理師なら成長する子どもの身体づくりを助ける存在として、やりが...

インターナショナルスクールに就職したい保育士さん必見!給料や仕事内容、有利な資格とは
保育士さんが活躍できる場所のひとつとしてインターナショナルスクールがあります。転職を検討するなかで、英語力は必須なのか、どんな資格が必要なのかなどが気になるかもしれません。今回は、インターナショナルス...

【2026年】保育士の借り上げ社宅制度とは?自己負担額と同棲・結婚後の条件を解説
保育士さんの家賃負担を軽減する「借り上げ社宅制度」。2025年度の制度改正で利用条件が変わり「制度がなくなる?いつまで使える?」「結婚してもOK?」といった疑問や不安も多いようです。本記事では、制度の...

児童館職員になるには?必要な資格や仕事内容、給料
児童館は、地域の子どもたちへの健全な遊び場の提供や子育て家庭の育児相談などを行なう重要な施設です。そんな児童館の職員になるにはどのような資格が必要なのかを解説します。また、児童館の先生の仕事内容や20...

病児保育とはどのような仕事?主な仕事内容や給与事情、働くメリットも解説
病児保育とは、保護者の代わりに病気の子どもを預かる保育サービスのことを言います。一般的に、風邪による発熱などで保育施設や学校に通えない子どもを持つ保護者が利用します。今回は、そんな病児保育の概要を詳し...

【2026年度】保育士の給料と年収は今後どうなる?処遇改善の昇給額と採用で年間30万円支給する地域も紹介!
保育士は「給料が低い」と言われるなか、処遇改善で人件費が10.7%引き上げられました。2025年度に公表された統計では、正社員の平均年収は約407万円、パートの時給1,370円へ改善。ただし「手取りが...

保育園の事務仕事がきつい理由TOP5!仕事内容や給料、業務で楽しいと感じることも紹介
保育園で事務職の仕事を知りたい方必見!仕事に就いてから後悔しないように、今回は、保育園事務の仕事内容や業務がきつい理由・楽しいと感じることTOP5をわかりやすく紹介します。給料や待遇、採用に向けた面接...

新生児介護職員として無資格で働くには?病院や乳児院などでの仕事について
新生児介護職員など、新生児のケアに携わる仕事に関心を持つ方には、無資格でも働けるのか気になる方がいるかもしれません。基本的に「新生児介護職員」という職種はありませんが、新生児のケアに関わる仕事を指すこ...

病児保育士になるには?必要な資格や資格の合格率、給料事情を解説
体調の優れない子どもを保護者の代わりに預かる病児保育士。そんな病児保育士になるには、一体どうすればよいのでしょうか。今回は病児保育士になるために必要な資格などを紹介しつつ、病児保育士として働ける職場や...

乳児院とは?果たす役割や子どもの年齢、現状と今後の課題など
乳児院とは、なんらかの理由で保護者との生活が困難な乳児を預かる施設です。一時保護やショートステイで滞在する場合もあり、保育士の求人もあります。そんな乳児院とはどんな施設なのか、厚生労働省の資料をもとに...

新しい働き方「総合職保育士」とは?仕事内容や働くメリット、給料事情など
総合職保育士という働き方をご存じでしょうか?近年注目されはじめている新しい働き方で、保育士以外の職種にキャリアを転換しやすいことが特徴です。今回は、総合職保育士について、仕事内容や給料事情、キャリアコ...

乳児院で働く職員の一日の流れは?仕事内容や年間行事、早番~夜勤の勤務時間まで
乳児院で働く職員の一日の流れや仕事内容とはどのようなものなのでしょうか。乳児院は24時間365日子どもたちを養育する施設であることから、交代制の勤務形態がほとんどです。今回は乳児院で働く職員の一日の流...

乳児院の給料はいくら?職員の資格別に平均給与を確認しておこう
乳児院は乳幼児期に適切な養育が受けられない乳児を保護し、健全な育成を図るための施設であり、医師や看護師、保育士などさまざまな資格を持つ職員が働いています。そんな乳児院の給料事情について、詳しく知りたい...

乳児院でボランティアとして活動したい!活動内容やボランティアを探す方法を紹介
乳児院は乳幼児期に適切な養育が受けられない乳児を保護し、健全な育成を図るための施設です。社会的に大きな意義のある施設だからこそ、その力になりたいとボランティアとしての活動を希望する場合もあるでしょう。...

保育士さんが乳児院を辞めたい理由。働き方や悩み、ひどいと感じる時とは
乳児院で働く保育士さんが辞めたいと感じるのはどんなときでしょうか。勤務体制、保育の内容などさまざまな問題で、ひどい・つらいと思うことがあるかもしれません。また、保育をする上で乳児院ならではの難しさもあ...

乳児院で働く看護師とは。役割や仕事内容、給料事情など
看護師資格を活かして働ける転職先の一つとして、乳児院を検討している方もいるかもしれません。しかし、そもそもどんな施設で、病院や保育園での仕事内容とどう違うのかなど気になりますよね。今回は、乳児院で働く...

保育において欠かせない養護とは?乳児期と幼児期のねらい
保育における養護は、子どもたちの健康管理を担うという役割だけではなく、子どもたちの心身の健やかな成長を支えるという大切な要素も含まれています。けれども、具体的な内容や対応の仕方について戸惑う方も多いの...

保育園における乳児保育について知っておこう。概要や保育士さんの役割
保育園で行なう乳児保育とは、どういったものなのでしょうか。乳児保育に興味を持っていながら、自分に向いているのか気になっている人もいるでしょう。今回は、保育園における乳児保育について、概要や保育士さんの...

乳児保育に興味がある保育士さん必見!やりがいや大変なこと
乳児保育に興味があるという保育士さんもいるのではないでしょうか。乳児保育とはどのようなものなのか特徴などをおさえておくと、就活の際に役立つかもしれません。今回は乳児保育を担当する保育士さんが感じる、や...

乳児向けのふれあい遊び。ねらいや効果、保育園で楽しめる人気の手遊び歌
乳児クラスでのコミュニケーションにぴったりなふれあい遊び。0歳児や1歳児、2歳児の子どもたちは、保育士さんとスキンシップを取りながら、わらべうたや手遊び歌を楽しんでくれるかもしれません。今回は、保育園...

【35選】乳児向けの室内遊びまとめ。保育のねらいや、ゲーム・製作など春夏秋冬のアイデア
雨の日や冬の寒い日、夏の日差しの強い日などは、保育園で乳児さんと室内遊びを楽しみましょう。今回は乳児(0歳児・1歳児・2歳児)クラスで楽しめる運動やゲーム性のある遊び、製作遊びのアイデア35選を紹介し...

保育士に人気の乳児保育。0~2歳児の赤ちゃんとの接し方や、働く上での魅力とは?
0~2歳児の赤ちゃんのみを対象とした乳児のみの保育園、なかでも小規模保育が、ここ数年で驚くほど増加しているのはご存じでしょうか?2017年3月の時点で設置数は2,553件。ここ2年間で約1.5倍ほど増...

乳児保育の現場での子どもの名前を呼ぶねらいとは?名前を覚えるための遊びも紹介
乳児保育の現場で、日常的に子どもの名前を呼びますが、そこには子どもの安心感を育み、信頼関係を築くための重要な役割が込められています。そもそも名前を呼ぶという行為は、子どもにどのような影響を与えるのでし...

資格なしで新生児ケアアシスタントとして働くには?新生児ケアに携わるために知っておきたいこと
保育関係の資格なしでも「新生児ケアアシスタント」という仕事に興味を持つ方がいるかもしれません。新生児ケアに関わる職種はさまざまありますが、実際には資格が必要な職種が多いのが現状です。今回は、資格なしで...

認定病児保育専門士になりたい!資格の取り方や役割など
病児保育における専門的な知識を持つ認定病児保育専門士。この資格を取得することで、保育士としてのキャリアが広がり、病児・病後児保育室などの活躍の場が一層増えるでしょう。この記事では、認定病児保育専門士の...

認定病児保育スペシャリストの資格の活かし方!就職に有利な仕事は?
認定病児保育スペシャリストの資格を活かして働きたいと考えている保育士さんもいるでしょう。保育士として、資格で得た知識を使える場面もあるかもしれません。今回は、認定病児保育スペシャリストの資格を持ってい...

【例文あり】病児保育士に転職したい!志望動機の書き方や働くメリットなど
発熱や病気で、保育園に登園できない子をスポットで預かるのが「病児保育施設」です。そんな病児保育士へ転職したい!でも、どうアピールすればよい?と、志望動機でつまずく保育士さんもいるようです。今回は、病児...

職場としての認定こども園の種類、保育士の働きやすさ
「認定こども園」とは、保育所と幼稚園それぞれの良さを生かした施設のことです。なんとなく知っていても、具体的な定義や仕事内容まで説明できる保育士さんは少ないのではないでしょうか?今回のコラムでは、認定こ...
- 同じカテゴリの記事一覧へ
社会人から保育士に!保育士資格取得の費用をおさえる方法

保育士資格取得のために2つのルートについて紹介しましたが、「学費が高そう」「費用が心配…」と感じる社会人も多いかもしれません。
しかし、保育士を目指す方向けの公的な支援制度を活用すれば、学費や生活費の負担を軽減できるケースもあります。
ここでは、保育士資格の取得を目指す社会人に知ってほしい3つの費用支援制度を紹介します。
教育訓練給付金(一般/専門実践)を活用する
教育訓練給付金は、雇用保険の加入歴がある方を対象に、厚生労働省が実施している学び直しの支援制度です。
保育士資格の取得に向けた講座も対象となり、条件を満たせば、受講費用の一部が支給されます。
教育訓練給付制度には、以下の3種類があります。※2025年7月時点
- 一般教育訓練給付金:通信講座などが対象で、受講費用の20%(上限10万円)が支給・保育士試験対策の講座の多くが該当しており、四谷学院なども対象例
- 特定一般教育訓練給付金:速やかな再就職やキャリア形成に資する講座が対象で、受講費用の40%(上限20万円)が支給されます。訓練修了後1年以内に就職した場合は、50%(上限25万円)まで支給
- 専門実践教育訓練給付金:大学・短大・専門学校などの養成校での受講が対象で、受講費用の50%(年間上限40万円)が支給
修了後1年以内に保育士として就職すれば、さらに20%(年間上限16万円)が加算されます。
一定の条件を満たし、厚生労働大臣の指定を受けた講座であれば、給付対象となります。
受講したい講座が見つかれば、ハローワークや厚生労働省の教育訓練講座検索システムで確認することが大切ですね。
自治体の「保育士修学資金貸付制度」をチェック
多くの自治体では、保育士を目指して養成校に通学する学生を対象に「保育士修学資金貸付制度」を設けています。
保育士の養成校への入学準備金・授業料・生活費などを無利子で貸し付けてもらえる制度です。
たとえば、東京都の制度の概要は以下の通りです。※2025年7月時点
【対象者】
以下の条件をすべて満たす方が対象です。
- 東京都内に住所を有し、20歳未満の子どもを扶養しているひとり親家庭の母または父
- 児童扶養手当の受給者、または同等の所得水準にある方
- 養成機関において6か月以上の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれる方
- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方
- 過去にこの給付金を受給していない方
【貸付金】
- 入学準備金:20万円以内
- 修学資金:月額5万円(最大2年間)
- 就職準備金:20万円以内
また、卒業後に一定期間、指定された地域の保育施設で保育士として働けば、返済が免除されます。
そのため「実質的に返さなくていい奨学金」といった役割を果たすケースも少なくありません。
制度の詳細や利用条件は自治体ごとに異なるため、お住まいの都道府県・市区町村の公式サイトで最新情報を確認するようにしましょう。
ひとり親家庭なら「高等職業訓練促進給付金」も
「高等職業訓練促進給付金」は、ひとり親家庭の方が看護師や保育士など、就職に有利な資格を取得するために活用できる公的制度です。
全国の自治体で実施されており、各地域によって支給額や条件が異なります。
たとえば、福岡県では以下のような支援が用意されています。※2025年7月時点
【対象者】
以下の条件をすべて満たす方が対象です。
- 福岡県内在住
- 児童扶養手当を受給中または同等の所得水準にあるひとり親の方
- 6カ月以上の養成機関に通い資格取得を目指している方が対象
- 所得が児童扶養手当受給対象水準である方(所得水準を超えた場合であっても1年に限り引き続き対象※令和6年8月30日以降)
養成機関において6か月以上修業予定である方
【支給額(月額)】
- 市町村民税非課税世帯:10万円(修業最終年は14万円)
- 市町村民税課税世帯:7万500円(修業最終年は11万500円)
【修了支援給付金(修了時に一括支給)】
- 非課税世帯:5万円
- 課税世帯:2万5千円
お住まいの都道府県・市区町村の公式サイトで内容をご確認ください。
社会人から保育士になる!よくある質問Q&A
保育士を目指す社会人の方から寄せられるよくある質問をまとめました。
保育士養成施設に通学する場合、期間はどれくらいかかりますか?
通信制の場合も最短2年で卒業できる学校がありますが、在籍期間や学習ペースによっては3年以上かかるケースもあります。
保育士になるのに年齢制限はありますか?
高校卒業以上の学歴があれば、何歳からでも保育士試験の受験や養成施設への入学が可能です。
実際に40代・50代から資格取得を目指す方も多く、子育て経験を活かして現場で活躍するケースもあります。
保育士試験の合格率はどのくらいですか?
一度合格した筆記科目は3年間有効なため、科目ごとの計画的な学習が合格のカギとなります。
社会人でも働きながら保育士を目指せますか?
通信講座や夜間の養成校などを活用し、自分のペースに合わせた学習が可能です。
未経験から保育士になるのは難しいですか?
現場経験がなくても、資格取得後にしっかりと実習や研修を通してスキルを身につけていけます。深刻な保育士不足のため、歓迎してくれる園がたくさんあるでしょう。
保育士の仕事は体力的に大変ですか?
ただし、自分のペースで無理なく働ける職場を選ぶことも可能です。たとえば、小規模保育園などは保育室がコンパクトで移動も少なく、体への負担が比較的少ない傾向があります。
保育士は給料はどれくらいもらえますか?
経験年数や役職によって給与アップが見込め、令和6年(2024年公表)の賃金構造基本統計調査によると、勤続年数8年ほどの保育士さんの平均月収は約26万9,700円、年間賞与は約70万8,200円で、年収に換算すると約324万5,600円です。
また、パート勤務の平均時給は1,348円とされており、園によって異なるものの、少しずつ給料が上がっていることが予想されます。
子育て経験は保育士の仕事に役立ちますか?
保護者対応や子どもの気持ちへの理解などを活かせるでしょう。
どのような人が保育士に向いていますか?
チームで連携を取って働く力や柔軟な対応力も求められるため、コミュニケーション能力が高い方にもぴったりですね!
社会人から保育士を目指して子どもと関わる仕事に就こう
保育士は、子どもの成長に寄り添い、笑顔を支えるやりがいのある仕事です。
社会人からのスタートでも、学び直しやキャリアチェンジとして多くの方が資格取得に挑戦しています。
「今からでも間に合うかな…」と不安に思っている方は、まずは自分のペースで学べる通信講座から始めてみませんか?
四谷学院の通信講座では、保育士試験の合格に向けたわかりやすい教材や個別サポート体制が整っており、働きながら学習に取り組んでいる方がたくさんいます!
また、資格取得後の就職先を探すなら、保育士バンク!のキャリアアドバイザーがしっかりサポート。
未経験OKの園やブランク歓迎の求人も豊富にあるため、保育士デビューをしっかり後押しします。
あなたも保育士資格の取得に向けて自分に合った方法で一歩を踏み出してみませんか?
子どもたちのそばで、かけがえのない時間をともに過ごせる未来をつくっていきましょう。
保育士バンク!で転職相談無料で会員登録する出典:保育士になるには/こども家庭庁出典:保育士試験合格者の就職状況等に関する調査研究研究報告書/厚生労働省出典:保育士試験の実施状況(令和5年度)/こども家庭庁出典:令和7年試験案内/一般社団法人 全国保育士養成協議会出典:教育訓練給付制度/厚生労働省出典:魅力ある保育/東京都福祉局出典:福岡県

保育士バンク!の新着求人
お住まいの地域を選択して、最新の求人情報をチェック!


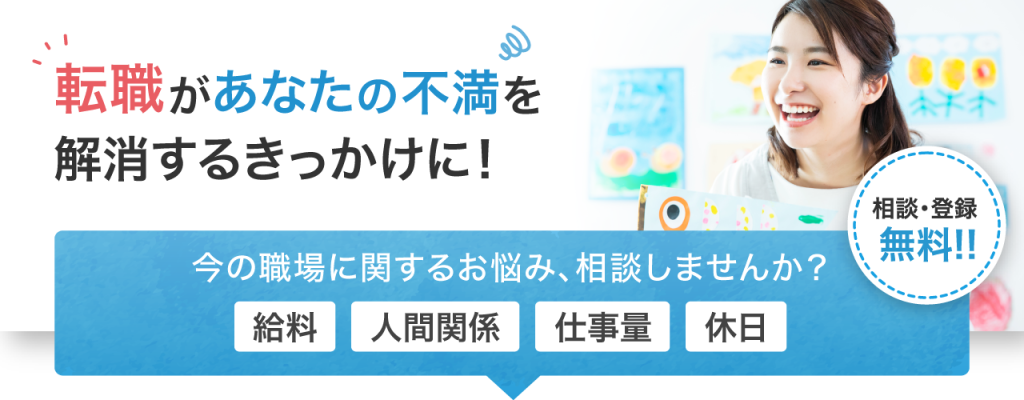





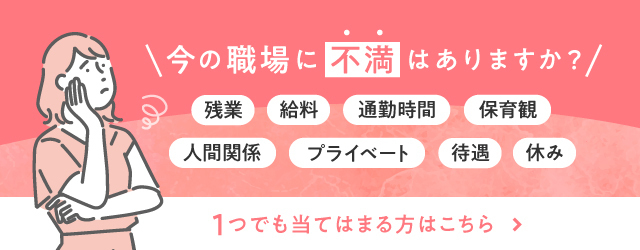
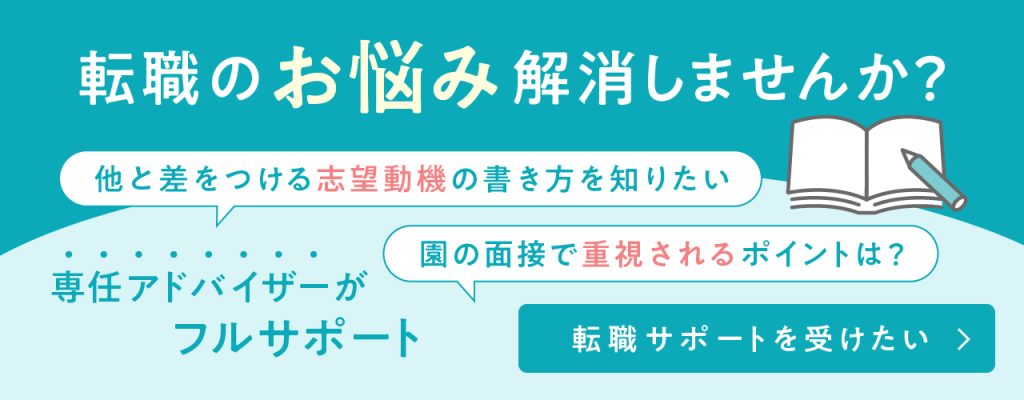
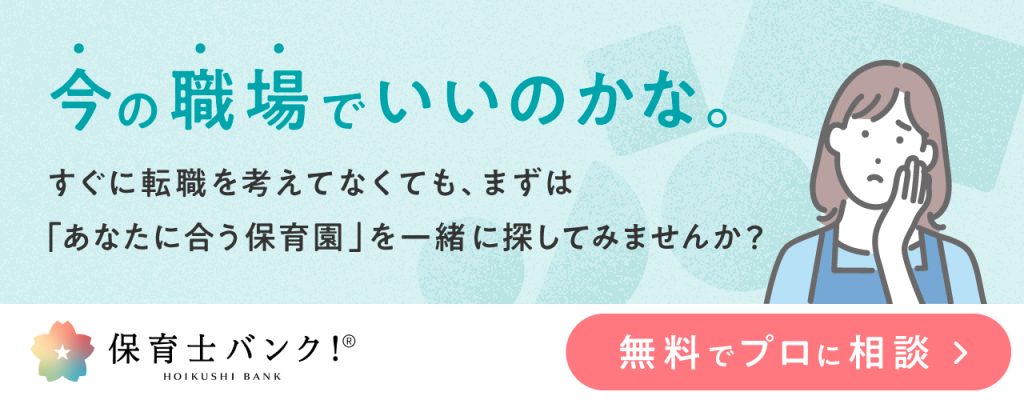
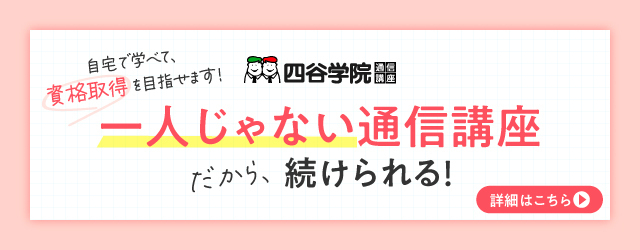
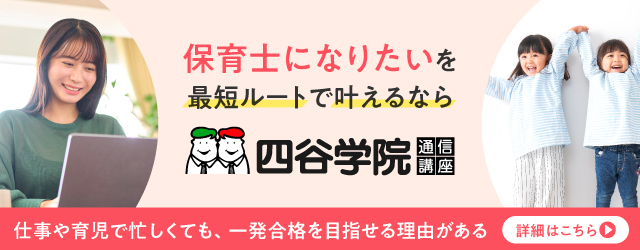







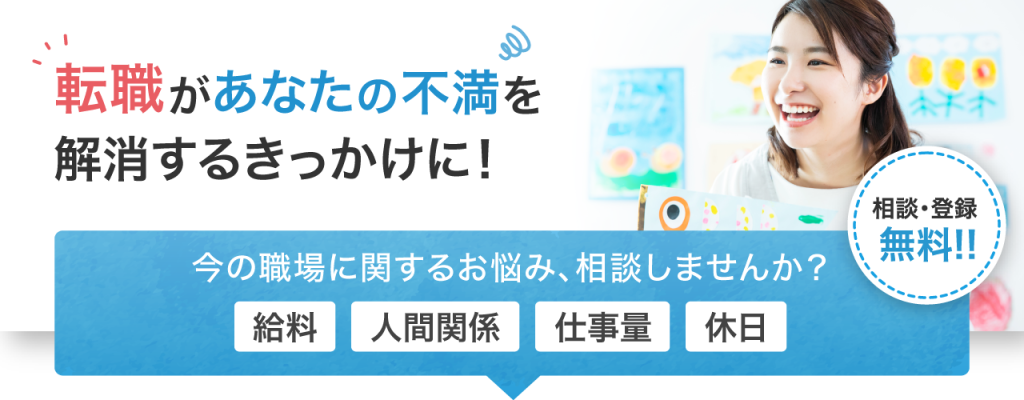





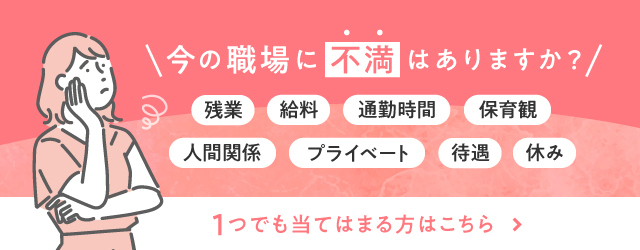
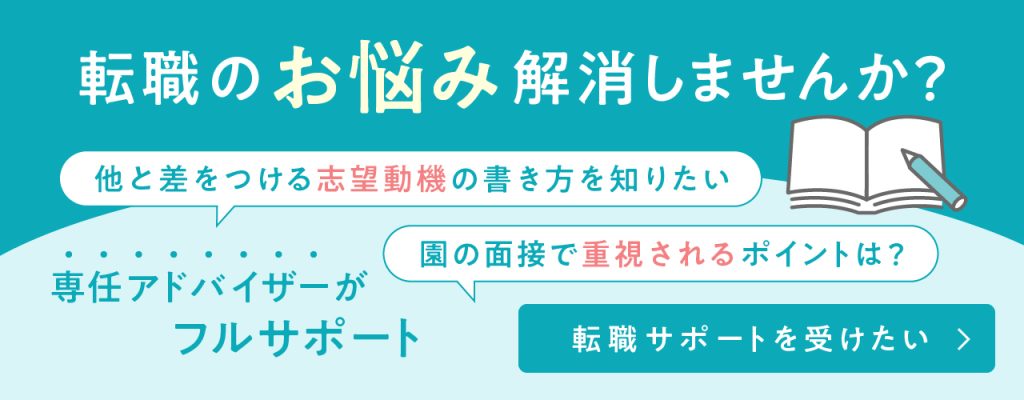
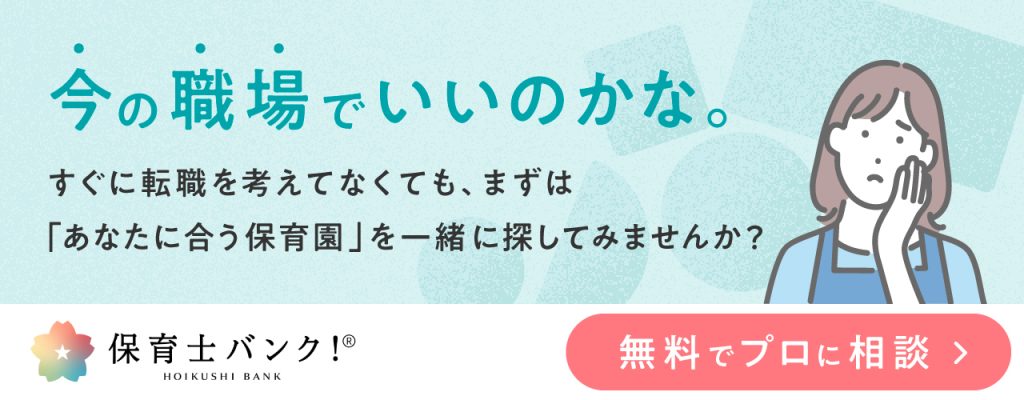
























/campaign/0004/DZ7TWBcJ3MWmgU6JV1RVa7zbReTDn5CSzSupdV30q4TVPaApz5heM6bnqp1TJkqs)