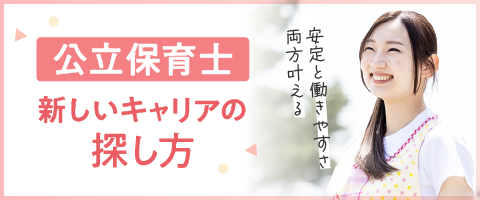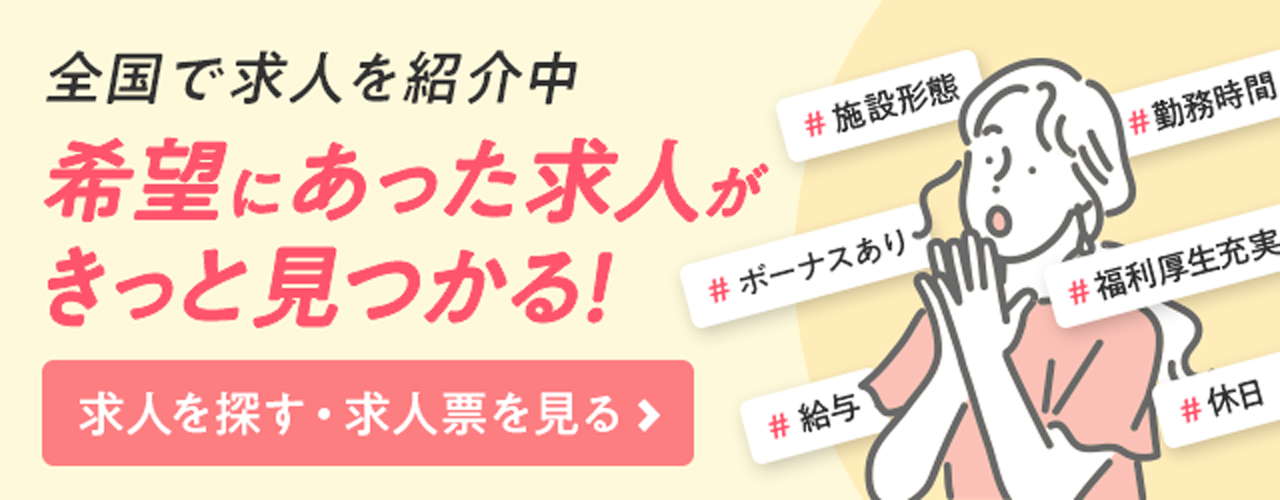2025年7月の保育ニュースを紹介!「浅い水場での事故」や「保育士の配置基準見直し」「外国人保育士の受け入れに関する提言」「保育園での心理的虐待」など、現場の安心・安全と保育の質の維持に関わる重要な話題をお届けします。各ニュースのコメント例も紹介しているので、会議や面接などでお役立てくださいね。
 Qiteng T / stock.adobe.com
Qiteng T / stock.adobe.com
【2025年7月の保育ニュース】水深2cm~3cmに潜む水遊び事故に注意!
7月に入り、水遊びやプール活動を取り入れる園も増えてきた頃。
水深の浅い場所でこどもが溺れるリスクもあることから、水の深さなどに関係なく、安全対策の見直しが急務です。
2025年6月にはこども家庭庁からも「プール活動・水遊びの事故防止及び熱中症事故の防止について」という通知が出され、保育・教育現場に向けて以下のような対応が呼びかけられました。
【プール活動・水遊びの際に注意すべきポイント】
- 監視者は監視に専念する。
- 監視エリア全域をくまなく監視する。
- 動かないこどもや不自然な動きをしているこどもを見つける。
- 規則的に目線を動かしながら監視する。
- 十分な監視体制の確保ができない場合については、プール活動の中止も選択肢とする。
- 時間的余裕をもってプール活動を行う。 等
水遊びは、こどもたちが夏ならではの感触を楽しんだり、友だちと関わったりできる大切な活動です。
ただ、楽しさが増すぶん、こどもの動きも活発になり、ちょっとした油断や見落としが事故につながる恐れもあるでしょう。
日々の保育の中で、「少し疲れていないかな?」「今日は水に入る前に一息入れたほうがいいかな?」といった気づきを大切にすることが、事故の予防につながるのかもしれません。
また、これからさらに暑さが厳しくなる時期。熱中症のリスクにも目を向けながら、こどもが安全に楽しく過ごせる環境を整えていけるとよいですね。
【このニュースのコメント例】
暑さが厳しいなかでこどもの水遊びやプール活動の頻度も増えてきました。
浅い水深でも溺水事故などが発生する恐れがあるため、「ここは大丈夫」という思い込みが一番の危険なのかもしれないと感じています。
実際、こどもたちは少し水に触れるだけでも夢中になって遊ぶので、ふとした拍子に転倒したり、水を飲み込んだりする場面もありそうです。
職員間で事前に見守り体制や活動の流れを確認する時間を持ち、安全管理の徹底を図りたいです。
「各職員がこどもを見守る位置」「こどもへの声をかけるタイミング」「体調を崩したときの連携方法」など、細かな点まで共有することも大切だと思います。
【2025年7月の保育ニュース】「外国人保育士の受け入れ」提言に現場から疑問の声も
2025年6月の一部の報道をきっかけに、「外国人保育士の受け入れ」が話題になっており、現場からはさまざまな意見が寄せられています。
背景には、慢性的な保育士不足があり、問題の解消に向けた一手として、今後は外国籍人材の活用も検討していくという流れがあるようです。
しかし、この提言に対して、「現場を知らない人の発想」などという声も聞かれます。
というのも、保育の現場では、こどもの発達段階や家庭環境に合わせた、丁寧で継続的な関わりが欠かせません。
また、日本ならではの保育の文化や、こどもとの言葉のやりとりも大切にされており、そうした積み重ねが保育の質の維持や向上につながっていると考えられています。
そのため、単に人手を増やすだけでは、保育士不足の本質的な解決にはつながらないという見方もあるのです。
これからも、保育士不足の課題にどのように向き合い、こどもの成長を支える環境を整えていくのか、制度のあり方が問われるでしょう。
【このニュースのコメント例】
「外国人保育士の受け入れ」という提言を知ったとき、戸惑いはありました。
保育士は単なる人手ではなく、こども一人ひとりの成長に寄り添い、日々の積み重ねの中で信頼関係を築いていく仕事だと思っています。
ただ、外国の方が保育の現場に入ること自体は、決してマイナスな面ばかりではなく、こどもたちにとって異文化に触れるきっかけになる可能性もあると感じました。
だからこそ、受け入れるかどうかではなく、「どうすればこどもたちが安心できる環境をつくりあげることができるのか」を考えていく必要があると思います。
これからも保育に関するニュースに目を向けながら、現場で大切にしていることを見失わずに保育と向き合っていきたいです。
簡単1分登録!転職相談
保育士・幼稚園教諭・看護師・調理師など
保育関連の転職のご質問や情報収集だけでもかまいません。
まずはお気軽にご相談ください!
【2025年7月の保育ニュース】保育士の配置基準問題。過疎地では緩和の方向へ。

こども家庭庁で、過疎地における保育士の配置基準を一部緩和する方向で検討に入ったと報じられています。
中山間地域や離島などでは、保育士の確保が厳しくなっており、地域の保育サービスをどのように維持していくかが大きな課題となっています。
また、現行の配置基準では、常勤保育士を「月120時間以上勤務する者」と定義していますが、この要件についても緩和を視野に入れた見直しが検討されています。
2025年7月時点の保育士の配置基準は以下の通りです。
- 【0歳児】3人につき保育士1人
- 【1・2歳児】6人につき保育士1人
- 【3歳児】20人につき保育士1人
- 【4・5歳児】25人につき保育士1人(※2024年度に30人→25人へと引き下げ)
このように、2024年度には保育士の配置基準が見直され、4・5歳児の基準が引き下げられました。
その一方で、都市部を含めた多くの園で保育士不足が続いており、「新しい基準を満たしたくても人手が足りない」という声も少なくありません。
制度の改善と現場の実情との間にギャップが生じている可能性があります。
配置基準の厳格な運用が保育の質を守る一方で、実際の保育現場に合わせた柔軟な対応も求められるでしょう。
地域によって置かれている状況はさまざまですが、「こどもにとって最善の環境とは何か」を、改めて考えるタイミングなのかもしれません。
【このニュースのコメント例】
人手が足りないと感じる場面は、どこの園でも少なからずあると思います。
こどもと丁寧に向き合いたい気持ちはあっても、職員の数が足りなければ、どうしても目が届きにくくなってしまう瞬間は避けられません。
保育士の配置基準は「こどもの育ちを安全に見守る」ための大切な目安です。
だからこそ、2024年度に4・5歳児の配置基準が引き下げられたことは、保育の質を高める上でもよろこばしい変化だと感じています。
一方で、「人を増やしたくても採用が難しい」「そもそも応募すら来ない」という状況が、地域によっては深刻化しているというニュースも見かけました。
配置基準の緩和にはいろいろな意見があると思いますが、どんな環境であっても「こどもが安心して過ごせる場であること」を第一に考えていきたいです。
そのためにも、職員同士で声をかけ合ったり、配置の工夫や休憩の取り方などを見直したりしながら、よりよい体制を目指していけたらと思います。
保育士バンク!の新着求人
お住まいの地域を選択して、最新の求人情報をチェック!
選択済みの市区町村
【2025年7月の保育ニュース】保育施設での「こどもへの心理的虐待」に注意!声かけの見直しと対策の重要性
一部の報道によれば、こどもの言動に対して繰り返し強い否定的な声かけを行ったことが「心理的虐待」にあたるとされた事例が報告されました。
保育の現場では、日々の声かけや関わり方についての見直しが求められています。
こども家庭庁は、「保育所等における心理的虐待の具体例」として、以下のような行為を挙げています。
- ことばや態度による脅かし、脅迫を行うなど
- 他のこどもとは著しく差別的な扱いをする
- こどもを無視したり、拒否的な態度を示したりするなど
- こどもの心を傷つけることを繰り返し言うなど(たとえば、日常的にからかう、「バカ」「あほ」など侮蔑的なことを言う、こどもの失敗を執拗に責めるなど)
- こどもの自尊心を傷つけるような言動を行うなど(たとえば、食べこぼしなどを嘲笑する、「どうしてこんなことができないの」などと言う、こどもの大切にしているものを乱暴に扱う、壊す、捨てるなど)
- 他のこどもと接触させないなどの孤立的な扱いを行う
- 感情のままに、大声で指示したり、叱責したりする など
こうしたガイドラインが通知されているにもかかわらず、現場ではその存在を知らない保育士さんも少なくないかもしれません。
また、心理的虐待の背景には、保育士一人ひとりが抱える業務の多さや、形式的な対応への過度なプレッシャーといった要因も考えられます。
こどもの心に与える影響をふまえながら、声かけについて各園で話し合いや研修の機会を設けることも大切です。
ただし、保育士さん自身の心身にゆとりをもってこどもと向き合えるよう、安心して働ける環境づくりを目指していくことも必要でしょう。
【このニュースのコメント例】
日々の保育の中で、こどもへの声かけについて迷う場面はたくさんあります。
こどもの年齢や性格、その時の寄り添い方により、かける言葉の選び方やタイミングも変わってくるため、簡単なことではないと感じます。
たとえば、跳び箱がなかなか飛べない子に「大丈夫だよ。できるよ!頑張って」と声をかけたとして…自分では励ましているつもりでも、こどもにとってはプレッシャーになることもあるかもしれません。
こどもたちにどのような声かけをしていくかは、その子の心や表情を感じ取り、どのように受け止めていくのかを考える必要があると思いました。
これからも、こどもの気持ちに寄り添いながら言葉選びを考え、保育士として経験を積んでいきたいと思います。
読んでおきたいおすすめ記事

【2026年版】乳児院で働くには?必要資格と給料、保育園との違いを解説
「乳児院で働くにはどうすればいいの?」と考える保育士さん必見!乳児院は、さまざまな事情で家庭で暮らせない0歳児~2歳頃の子どもを24時間体制で養育する施設です。保育士の方は仕事内容や保育園との違いなど...

子どもと関わる仕事31選!必要な資格や保育士以外の異業種、赤ちゃんや子ども関係の仕事の魅力
子どもや赤ちゃんと関わる仕事というと保育士や幼稚園の先生を思い浮かべますが、子どもに関係する仕事は意外とたくさんあります!今回は赤ちゃんや子どもと関わる仕事31選をご紹介します。職種によって対応する子...

企業内保育所とは?持ち帰り仕事ゼロの理由と仕事内容のリアル!給料や選び方も解説
企業内保育所とは、主に企業の従業員の子どもを預かる施設。行事や書類業務が少なく、少人数の子どもの成長を見守りながら、やりがいを感じる保育士さん多数!認可保育園との違いを「比較表」で解説し、仕事内容や実...

託児所とは?保育園との違いや施設の種類、働くメリットや給料についてわかりやすく解説
託児所とは、さまざまな形態の認可外保育園のことを指します。主に企業内や病院で行われる小規模保育や、商業施設内に開設されている一時保育などがあたりますが、保育士さんとしては、一般的な園との違いや働きやす...

保育士の年度途中退職は「無責任」ではない!法律で守られた権利と円満退職に向けた5ステップ
「担任だから年度途中で辞められない」と自分を責めていませんか?実は、保育士の途中退職は法律で認められた正当な権利です。今回は就業規則より優先される「民法の知識」や、円満退職に向けた5ステップ、実際に年...

保育士をサポート・支える仕事特集!保育補助や事務、運営スタッフなど多様な職種を紹介
保育士のサポート役として働きたいという方はいませんか?保育補助や事務、本社勤務の運営スタッフなどさまざまな仕事があるため、保育士さんを支える仕事を一挙紹介!異業種である保育士人材のキャリアアドバイザー...

保育士を辞める!次の仕事は?キャリアを活かせるおすすめ転職先7選!転職事例も紹介
保育士を辞めたあとに次の仕事を探している方に向けて、資格や経験を活かせる仕事を紹介します。ベビーシッターなど子どもと関わる仕事はもちろん、一般企業での事務職や保育園運営会社での本社勤務といった道も選べ...

病院内保育とは?働くメリットや1日のスケジュール、一般的な保育施設との違いについて紹介!
病院内保育とは、病院や医療施設の中、または隣接する場所に設置されている保育園のことです。保育園の形態のひとつであり、省略して院内保育と呼ばれることもあります。転職を考えている保育士さんの中には、病院内...

フリーランス保育士として自分らしく働くには。働き方、収入、仕事内容からメリットまで解説
保育園から独立して働くフリーランス保育士。具体的な仕事内容や働き方、給料などが気になりますよね。今回は、特定の保育施設に勤めずに働く「フリーランス保育士」についてくわしく紹介します。あわせて、フリーラ...

保育園の調理補助に向いてる人の特徴とは?仕事内容ややりがい・大変なこと
保育園で働く調理補助にはどのような人が向いてるのでしょうか。子どもや料理が好きなど、求められる素質を押さえて自己PRなどに活かしましょう。また、働くうえでのやりがいや大変なことなども知って、仕事への理...

子どもと関わる看護師の仕事10選!保育園など病院以外で働く場所も紹介
子どもに関わる仕事がしたいと就職・転職先を探す看護師さんはいませんか?「小児科の経験を活かして保育園に転職した」「看護師の資格を活用してベビーシッターをしている」など保育現場で活躍している方はたくさん...

保育士から転職!人気・おすすめの異業種20選。経験を活かす仕事ランキングや保育士以外の業種を紹介
保育士として働いていると、「保育士以外の仕事にチャレンジしてみたい」「異業種へ転職したい。事務・販売...保育士資格は活かせる?」などと考える方はいませんか?「保育士経験しかないけれど大丈夫?」と迷う...

【保育士の意外な職場30選】一般企業・病院からフリーランスまで!珍しい求人総まとめ
保育士資格を活かして働ける意外な職場は多く、病院、一般企業、サービス業などたくさんあります!今回は、保育園以外の転職先として人気の「企業内・院内保育」から異業種の「フォトスタジオ」「保育園運営本部」ま...

【2026年最新版】幼稚園教諭免許は更新が必要?廃止や有効期限切れの場合の対処法をわかりやすく解説
幼稚園教諭免許更新制については、2022年7月1日に廃止されました。以降は多くの教員免許が「更新不要・期限なし」として扱われるようになりました。ただし、制度廃止前にすでに失効していた免許状には、再授与...

保育士が児童発達支援管理責任者(児発管)になるには?実務経験や要件、働ける場所など
保育士の実務経験を活用して目指すことができる「児童発達支援管理責任者(児発管)」について徹底解説!多くの障がい児施設で人材不足が続いているため、児童発達支援管理責任者(児発管)を募集する施設が多数!2...

幼稚園教諭からの転職先18選!資格を活かせる魅力的な仕事特集
仕事量の多さや継続して働くことへの不安などを抱え、幼稚園教諭としての働き方を見直す方はいませんか。幼稚園教諭の転職を検討中の方に向けて、経験やスキルを活かせる18の職場を紹介します。保育系の仕事から一...

【2026年最新】放課後児童支援員の給料はいくら?年代別の年収やこの先給与は上がるのかを解説
放課後児童クラブや児童館などで働く資格職「放課後児童支援員」の平均給料はいくらなのでしょうか。放課後児童クラブで働く職員は資格の有無を問わず「学童支援員」と呼ばれ、給与が低いイメージがあるようですが、...

【2026年最新】保育士の給料は本当に上がる?正社員やパートの昇給額や「上がらない」と感じてしまう理由
「処遇改善で給料が上がるって聞いたのに、実感がない…いつ上がるの?」そんな声が、保育現場から聞こえる中、政府は保育士の人件費を10.7%引き上げるために、処遇改善制度を新たにスタート!2025年4月か...

私って保育士に向いていないかも。そう感じる人の7つの特徴や性格、自信を取り戻す方法
せっかく保育士になったのに「この仕事に向いていないのでは?」と不安を抱いてしまう方は多いようです。子どもにイライラしたり、同僚や保護者と上手くコミュニケーションが取れなかったりすると、仕事に自信が持て...

ベビーシッターとして登録するなら「キズナシッター」を選びたい理由トップ5
ベビーシッターとしてマッチングサービスに登録する際に、サイト選びに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。収入や働き方の安定性、サービスごとの特徴や魅力も気になりますよね。本記事ではそんななか「キズナ...

子育て支援センターで働くには?職員になるための資格や保育士の役割・仕事内容をわかりやすく解説!
子育て支援センターとは、育児中の保護者と子どもをサポートする地域交流の場。保育士経験者は資格を活かして働けるため、転職先のひとつとして考えることも大切です。今回は、職員になるための資格や保育士の役割、...

ベビーシッターになるには?資格や仕事内容、向いている人の特徴
ベビーシッターになるにはどうすればいいのでしょうか?まずは必要な資格やスキルをチェックしましょう。ベビーシッターは働く時間や場所を柔軟に調整できる場合が多く、副業としても人気です!初めてでも安心してベ...

【2026年最新】子育て支援員とは?資格取得の方法・研修、仕事内容などについて解説
「子育て支援員」は、保育や福祉の現場で子どもたちの成長を支える重要な資格です。2026年現在、放課後児童クラブや保育園では人材不足が続いており、子育て支援員のニーズはますます高まっているようです。この...

【2026年版】保育士の転職時期はいつ?年度途中の退職・4月入職のスケジュール
「そろそろ転職したいけれど、いつ動くのが一番いいんだろう…?」そんな不安を感じている保育士さんにとって、安心して転職を進められるベストタイミングは4月(=3月末退職)です。今回は、4月転職が最適な理由...

【2026年版】幼稚園教諭免許の更新をしていない!期限切れや休眠状態の対応、窓口などを紹介
所有する幼稚園教諭免許が期限切れになった場合の手続きの方法を知りたい方もいるでしょう。更新制の廃止も話題となりましたが、更新していない方は今後の対応方法をくわしく把握しておくことが大切です。今回は、幼...

【2026年最新】調理師の給料、年収はどれくらい?仕事内容や求人、志望動機なども徹底解説
子どもたちが毎日口にする給食やおやつを作る保育園の調理師。保育園で常勤として働く場合、年収は300万円以上が相場のようです。さらに、保育園調理師なら成長する子どもの身体づくりを助ける存在として、やりが...

インターナショナルスクールに就職したい保育士さん必見!給料や仕事内容、有利な資格とは
保育士さんが活躍できる場所のひとつとしてインターナショナルスクールがあります。転職を検討するなかで、英語力は必須なのか、どんな資格が必要なのかなどが気になるかもしれません。今回は、インターナショナルス...

【2026年】保育士の借り上げ社宅制度とは?自己負担額と同棲・結婚後の条件を解説
保育士さんの家賃負担を軽減する「借り上げ社宅制度」。2025年度の制度改正で利用条件が変わり「制度がなくなる?いつまで使える?」「結婚してもOK?」といった疑問や不安も多いようです。本記事では、制度の...

児童館職員になるには?必要な資格や仕事内容、給料
児童館は、地域の子どもたちへの健全な遊び場の提供や子育て家庭の育児相談などを行なう重要な施設です。そんな児童館の職員になるにはどのような資格が必要なのかを解説します。また、児童館の先生の仕事内容や20...

病児保育とはどのような仕事?主な仕事内容や給与事情、働くメリットも解説
病児保育とは、保護者の代わりに病気の子どもを預かる保育サービスのことを言います。一般的に、風邪による発熱などで保育施設や学校に通えない子どもを持つ保護者が利用します。今回は、そんな病児保育の概要を詳し...

【2026年度】保育士の給料と年収は今後どうなる?処遇改善の昇給額と採用で年間30万円支給する地域も紹介!
保育士は「給料が低い」と言われるなか、処遇改善で人件費が10.7%引き上げられました。2025年度に公表された統計では、正社員の平均年収は約407万円、パートの時給1,370円へ改善。ただし「手取りが...

保育園の事務仕事がきつい理由TOP5!仕事内容や給料、業務で楽しいと感じることも紹介
保育園で事務職の仕事を知りたい方必見!仕事に就いてから後悔しないように、今回は、保育園事務の仕事内容や業務がきつい理由・楽しいと感じることTOP5をわかりやすく紹介します。給料や待遇、採用に向けた面接...

新生児介護職員として無資格で働くには?病院や乳児院などでの仕事について
新生児介護職員など、新生児のケアに携わる仕事に関心を持つ方には、無資格でも働けるのか気になる方がいるかもしれません。基本的に「新生児介護職員」という職種はありませんが、新生児のケアに関わる仕事を指すこ...

病児保育士になるには?必要な資格や資格の合格率、給料事情を解説
体調の優れない子どもを保護者の代わりに預かる病児保育士。そんな病児保育士になるには、一体どうすればよいのでしょうか。今回は病児保育士になるために必要な資格などを紹介しつつ、病児保育士として働ける職場や...

乳児院とは?果たす役割や子どもの年齢、現状と今後の課題など
乳児院とは、なんらかの理由で保護者との生活が困難な乳児を預かる施設です。一時保護やショートステイで滞在する場合もあり、保育士の求人もあります。そんな乳児院とはどんな施設なのか、厚生労働省の資料をもとに...

新しい働き方「総合職保育士」とは?仕事内容や働くメリット、給料事情など
総合職保育士という働き方をご存じでしょうか?近年注目されはじめている新しい働き方で、保育士以外の職種にキャリアを転換しやすいことが特徴です。今回は、総合職保育士について、仕事内容や給料事情、キャリアコ...

乳児院で働く職員の一日の流れは?仕事内容や年間行事、早番~夜勤の勤務時間まで
乳児院で働く職員の一日の流れや仕事内容とはどのようなものなのでしょうか。乳児院は24時間365日子どもたちを養育する施設であることから、交代制の勤務形態がほとんどです。今回は乳児院で働く職員の一日の流...

乳児院の給料はいくら?職員の資格別に平均給与を確認しておこう
乳児院は乳幼児期に適切な養育が受けられない乳児を保護し、健全な育成を図るための施設であり、医師や看護師、保育士などさまざまな資格を持つ職員が働いています。そんな乳児院の給料事情について、詳しく知りたい...

乳児院でボランティアとして活動したい!活動内容やボランティアを探す方法を紹介
乳児院は乳幼児期に適切な養育が受けられない乳児を保護し、健全な育成を図るための施設です。社会的に大きな意義のある施設だからこそ、その力になりたいとボランティアとしての活動を希望する場合もあるでしょう。...

保育士さんが乳児院を辞めたい理由。働き方や悩み、ひどいと感じる時とは
乳児院で働く保育士さんが辞めたいと感じるのはどんなときでしょうか。勤務体制、保育の内容などさまざまな問題で、ひどい・つらいと思うことがあるかもしれません。また、保育をする上で乳児院ならではの難しさもあ...

乳児院で働く看護師とは。役割や仕事内容、給料事情など
看護師資格を活かして働ける転職先の一つとして、乳児院を検討している方もいるかもしれません。しかし、そもそもどんな施設で、病院や保育園での仕事内容とどう違うのかなど気になりますよね。今回は、乳児院で働く...

保育において欠かせない養護とは?乳児期と幼児期のねらい
保育における養護は、子どもたちの健康管理を担うという役割だけではなく、子どもたちの心身の健やかな成長を支えるという大切な要素も含まれています。けれども、具体的な内容や対応の仕方について戸惑う方も多いの...

保育園における乳児保育について知っておこう。概要や保育士さんの役割
保育園で行なう乳児保育とは、どういったものなのでしょうか。乳児保育に興味を持っていながら、自分に向いているのか気になっている人もいるでしょう。今回は、保育園における乳児保育について、概要や保育士さんの...

乳児保育に興味がある保育士さん必見!やりがいや大変なこと
乳児保育に興味があるという保育士さんもいるのではないでしょうか。乳児保育とはどのようなものなのか特徴などをおさえておくと、就活の際に役立つかもしれません。今回は乳児保育を担当する保育士さんが感じる、や...

乳児向けのふれあい遊び。ねらいや効果、保育園で楽しめる人気の手遊び歌
乳児クラスでのコミュニケーションにぴったりなふれあい遊び。0歳児や1歳児、2歳児の子どもたちは、保育士さんとスキンシップを取りながら、わらべうたや手遊び歌を楽しんでくれるかもしれません。今回は、保育園...

【35選】乳児向けの室内遊びまとめ。保育のねらいや、ゲーム・製作など春夏秋冬のアイデア
雨の日や冬の寒い日、夏の日差しの強い日などは、保育園で乳児さんと室内遊びを楽しみましょう。今回は乳児(0歳児・1歳児・2歳児)クラスで楽しめる運動やゲーム性のある遊び、製作遊びのアイデア35選を紹介し...

保育士に人気の乳児保育。0~2歳児の赤ちゃんとの接し方や、働く上での魅力とは?
0~2歳児の赤ちゃんのみを対象とした乳児のみの保育園、なかでも小規模保育が、ここ数年で驚くほど増加しているのはご存じでしょうか?2017年3月の時点で設置数は2,553件。ここ2年間で約1.5倍ほど増...

乳児保育の現場での子どもの名前を呼ぶねらいとは?名前を覚えるための遊びも紹介
乳児保育の現場で、日常的に子どもの名前を呼びますが、そこには子どもの安心感を育み、信頼関係を築くための重要な役割が込められています。そもそも名前を呼ぶという行為は、子どもにどのような影響を与えるのでし...

資格なしで新生児ケアアシスタントとして働くには?新生児ケアに携わるために知っておきたいこと
保育関係の資格なしでも「新生児ケアアシスタント」という仕事に興味を持つ方がいるかもしれません。新生児ケアに関わる職種はさまざまありますが、実際には資格が必要な職種が多いのが現状です。今回は、資格なしで...

認定病児保育専門士になりたい!資格の取り方や役割など
病児保育における専門的な知識を持つ認定病児保育専門士。この資格を取得することで、保育士としてのキャリアが広がり、病児・病後児保育室などの活躍の場が一層増えるでしょう。この記事では、認定病児保育専門士の...

認定病児保育スペシャリストの資格の活かし方!就職に有利な仕事は?
認定病児保育スペシャリストの資格を活かして働きたいと考えている保育士さんもいるでしょう。保育士として、資格で得た知識を使える場面もあるかもしれません。今回は、認定病児保育スペシャリストの資格を持ってい...

【例文あり】病児保育士に転職したい!志望動機の書き方や働くメリットなど
発熱や病気で、保育園に登園できない子をスポットで預かるのが「病児保育施設」です。そんな病児保育士へ転職したい!でも、どうアピールすればよい?と、志望動機でつまずく保育士さんもいるようです。今回は、病児...

職場としての認定こども園の種類、保育士の働きやすさ
「認定こども園」とは、保育所と幼稚園それぞれの良さを生かした施設のことです。なんとなく知っていても、具体的な定義や仕事内容まで説明できる保育士さんは少ないのではないでしょうか?今回のコラムでは、認定こ...
- 同じカテゴリの記事一覧へ
【2025年7月の保育ニュース】「叱るの先にあるもの」ある保育士の現場での一日をヒントに
日々の保育の中で、こどもを叱らなければならない場面に出会うことは少なくありません。
しかし、叱ることの本当の目的は何なのか…その「先」にあるものを見つめ直すことで、こどもとの関係は変わってくるのかもしれません。
保育士バンク!YouTubeチャンネルで紹介している密着動画では、こどもとの関わり方や葛藤、その中で得た気づきなどが語られています。
動画ではこどもへの接し方について、以下のポイントが挙げられています。
- 叱ることの目的は、こどもを責めることではなく、成長を促すためのもの
- 感情的な叱責ではなく、冷静に事実を伝えることが大切
- こどもの気持ちに寄り添い、共感する姿勢が信頼関係を築く
- 叱った後のフォローが、こどもの安心感につながる
「叱って終わり」ではなく、「叱った後、どう関わるか」を丁寧に考えることが、こどもの心の成長にとっても重要であるという視点を大切にしていました。
なお、保育士バンク!のYouTubeチャンネルでは、その他に保育士さんの1日の密着動画を多数紹介しています。
現場に立つ保育士さんは、他園の保育の様子をじっくり見る機会は少ないかもしれません。
日々の保育に役立つヒントがたくさん詰まっているので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
【このニュースのコメント例】
日々の保育の中で、叱る場面に立ち会うことは少なからずあります。
「これは伝えたほうがいい」「どうすれば伝わるかな」そんなふうに迷いながら、こどもと向き合っている方も多いのではないでしょうか。
動画を見て、「叱ること」が目的ではなく、その先にあるこどもの気持ちや成長を見つめることが大切なんだと、改めて気づかされました。
感情的になりそうなときこそ、一度立ち止まって、こどもの目線で感じてみること。
そして、叱った後に「ちゃんと見てるよ」「大丈夫だよ」と伝えることで、信頼関係をつないでいけるのだと思います。
これからも、自分の声かけや関わり方を振り返りながら、こどもたちにとって安心できる存在でありたいと思いました。
出典:教育・保育施設等におけるプール活動・水遊びの事故防止及び熱中症事故の防止について/こども家庭庁出典:保育所等における常勤保育士及び短時間保育士の定義について(通知)/こども家庭庁出典:幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する命令等の施行について(通知)/こども家庭庁出典:保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン/こども家庭庁
7月の保育ニュースをチェックして保育に役立てよう
2025年7月の保育ニュースでは、「外国人保育士の受け入れ」に関する提言や、「心理的虐待」に該当するとされた事例の報道など、保育のあり方を考えるきっかけとなる話題が取り上げられました。
社会の変化や保護者の方の価値観が多様化するなかで、保育現場では日々の活動を振り返りながら、こどもにとってよりよい環境づくりに取り組んでいくことが求められています。
職員会議や面接、日常の会話の中でも、保育に関する時事ニュースが話題になることがあるかもしれません。
日ごろから保育に関連する情報に触れておくことで、自分の考えを整理したり、保育観を深めたりするヒントにもつながるため、ぜひご活用くださいね。
なお、保育士バンク!では、保育士さんが楽しく働ける職場を探すお手伝いをしています。あなたらしく、自分の保育観に合った職場を見つけるためにまずはお気軽にご相談くださいね。新規オープン園や非公開求人など幅広く紹介させていただきます!
会員登録・相談無料保育士バンク!で転職相談

保育士バンク!の新着求人
お住まいの地域を選択して、最新の求人情報をチェック!


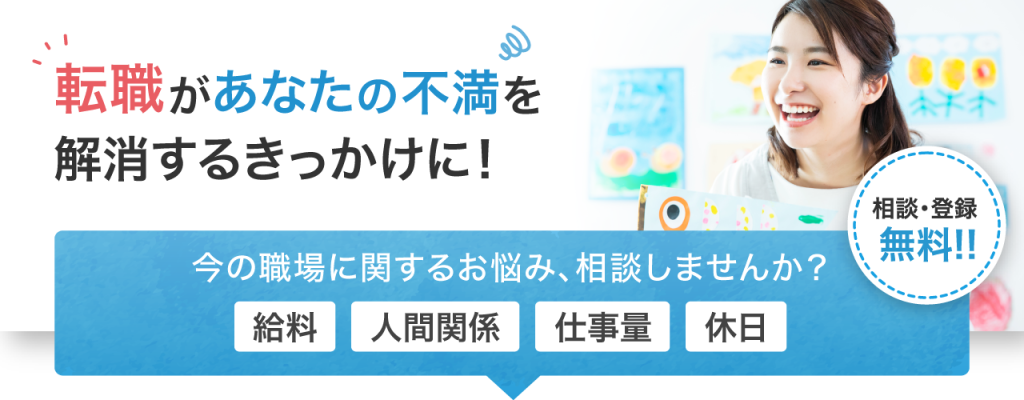





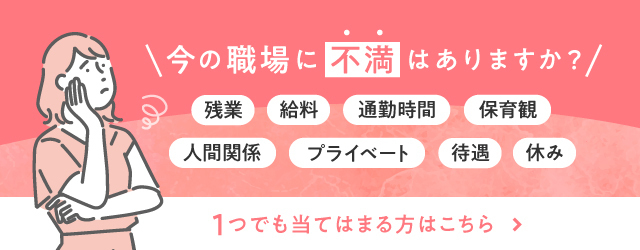
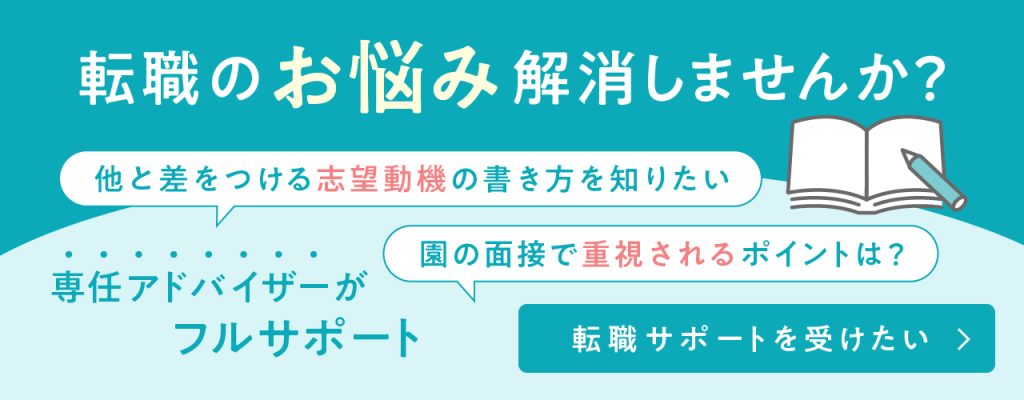
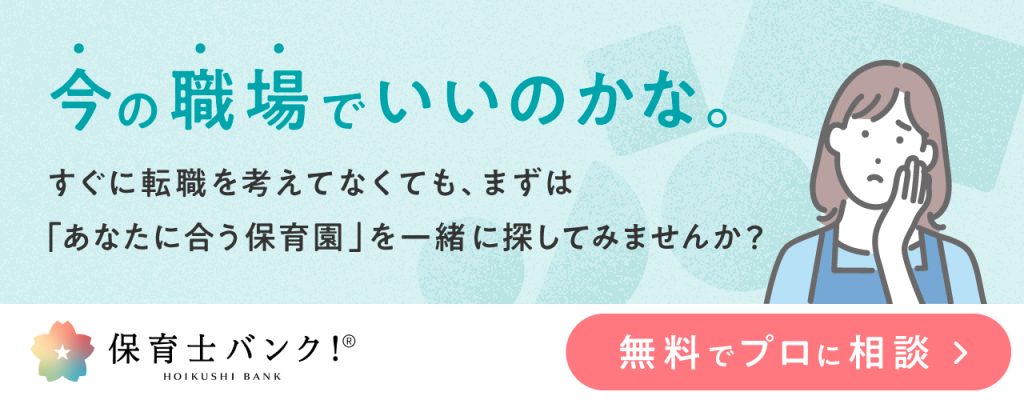
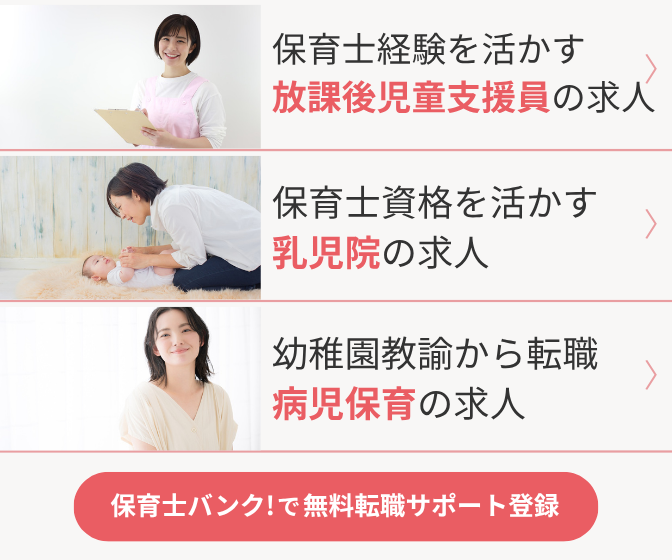




















/campaign/0004/DZ7TWBcJ3MWmgU6JV1RVa7zbReTDn5CSzSupdV30q4TVPaApz5heM6bnqp1TJkqs)